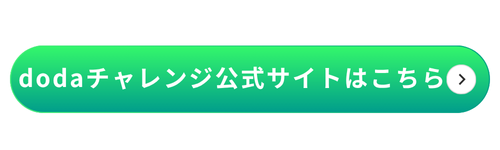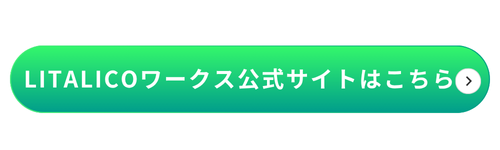dodaチャレンジの口コミはどう?障害者雇用の特徴やメリット・デメリットをやさしく解説

目次
- dodaチャレンジ障害者雇用の口コミや特徴は?おすすめのポイントを紹介します
- dodaチャレンジの口コミは?dodaチャレンジのメリットや他の就活サービスより優れているポイントは?
- dodaチャレンジの口コミやデメリットについて調査しました
- dodaチャレンジの口コミはどう?dodaチャレンジのサービスを実際に利用した人の口コミ・評判は?
- 良い口コミ1・面談では『どんな配慮があると働きやすいですか?』って具体的に聞いてくれて、企業にもそのまま伝えてくれたので、面接でも安心して話せました。
- 良い口コミ2・事務職ばかりかと思ったら、IT系のエンジニア職や専門職の求人もたくさん紹介されました。しかも、大手企業の求人もあって驚きました
- 良い口コミ3・転職した後も、月1回のペースでフォロー面談があって、悩みを聞いてくれました。自分では言いづらい職場の困りごとも、担当者がうまく伝えて調整してくれて、とても助かりました
- 良い口コミ4・私は東北在住ですが、オンライン面談でスムーズにサポートしてもらえました。リモートワークOKの求人も紹介されて、地方でも選択肢があるんだと感じました
- 良い口コミ5・障害者雇用だと単純作業ばかりと思っていましたが、スキルアップやキャリアアップも考えて求人を探してくれました。
- 悪い口コミ1・担当者によっては、障害への理解があまり深くないと感じたことがあります。『もっと詳しく説明しないといけないの?』と不安になりました
- 悪い口コミ2・事務系やIT系以外の職種が少ない印象を受けました。もう少しクリエイティブ系や他業種の求人も増えたらいいなと思います
- 悪い口コミ3・フォローはあると言われたのですが、転職後こちらから連絡しないと音沙汰がなかった…。自分から積極的に連絡を取る必要があるなと感じました
- 悪い口コミ4・地方在住ですが、リモートOKの求人は少なく、結局関東や関西の案件が多かったです。地元企業の求人はあまり見つかりませんでした
- 悪い口コミ5・キャリアアップを目指したいと思っても、スキルや経験が不足していると難しい求人が多かったです。未経験者向けのキャリア支援ももっとあればいいのに、と思いました。
- dodaチャレンジの口コミはどう?内定率・採用率はどう?求人が多い職種について
- dodaチャレンジの口コミは?dodaチャレンジの利用方法・登録方法について解説します
- dodaチャレンジの登録方法1・dodaチャレンジ公式サイトへログイン/「会員登録する」をクリック
- dodaチャレンジの登録方法2・基本情報を入力/入力後「登録する」をクリック
- dodaチャレンジの登録方法3・現在の状況についてチェックして登録
- dodaチャレンジの担当キャリアアドバイザーとの予約方法について
- dodaチャレンジの求人紹介の流れについて/キャリアアドバイザーがあなたに合う求人をピックアップしてくれる
- dodaチャレンジの書類作成・応募・面接サポートの流れについて
- dodaチャレンジの面接~内定までの流れ
- dodaチャレンジの入社からその後のフォローの流れについて
- dodaチャレンジの登録に必要なものを紹介します/面談までに準備しておくとスムーズです
- dodaチャレンジの口コミは?dodaチャレンジの解約方法や解約前の注意点について解説します
- 解約前の注意点1・アカウント削除するとサポートが完全に終了する
- 解約前の注意点2・応募中の企業があればキャンセル連絡を忘れずにしましょう
- 解約前の注意点3・内定後のアフターフォローが受けられなくなります
- 解約前の注意点4・アカウント情報は完全に削除され復元はできない
- 解約前の注意点5・他のサービスとの併用も検討してから決めましょう
- dodaチャレンジの解約(退会)の流れを解説します
- dodaチャレンジの口コミや評判はやばい!?怪しいなど悪い噂の理由について検証しました
- 理由1・障がい者専門の転職エージェントという特殊性が怪しく感じる人がいる
- 理由2・登録後に連絡が頻繁に来た・しつこい電話やメールがあるとの口コミが一部ある
- 理由3・成果報酬型(企業から報酬をもらう)のビジネスモデルへの不信感を持つ人がいる
- 理由4・求人が偏っている、求人数に限界があると感じる人がいる
- 理由5・内定がもらえないと不満を持つ人がいる
- dodaチャレンジの口コミは?dodaチャレンジの会社概要について紹介します
- dodaチャレンジの口コミはどう?についてよくある質問
- dodaチャレンジの口コミや評判について教えてください
- dodaチャレンジの求人で断られてしまったらどうすれば良いですか?
- dodaチャレンジで面談後に連絡なしの理由について教えてください
- dodaチャレンジの面談の流れや聞かれることなどについて教えてください
- dodaチャレンジとはどのようなサービスですか?特徴について詳しく教えてください
- 障がい者手帳を持っていないのですが、dodaチャレンジのサービスは利用できますか?
- dodaチャレンジに登録できない障害はありますか?
- dodaチャレンジの退会(登録解除)方法について教えてください
- dodaチャレンジのキャリアカウンセリングはどこで受けられますか?
- dodaチャレンジの登録には年齢制限がありますか?
- 離職中ですがdodaチャレンジのサービスを利用できますか?
- 学生ですがdodaチャレンジのサービスを利用できますか?
- dodaチャレンジの口コミは?その他の障がい者就職サービスと比較
- dodaチャレンジの口コミは?障害者雇用の特徴・メリット・デメリットまとめ
dodaチャレンジ障害者雇用の口コミや特徴は?おすすめのポイントを紹介します
「障害があっても、自分らしく働きたい」と願う方にとって、信頼できる転職支援サービスの存在は非常に心強いものです。
中でも「dodaチャレンジ」は、障がいのある方の就職・転職を専門に支援しており、多くの利用者から高評価を得ているサービスです。
ここでは、その特徴や魅力について、実際の口コミに基づきながらご紹介していきます。
特徴1・「dodaチャレンジ」のコンサルタントは障がいのある方に特化したプロ
dodaチャレンジの最大の強みは、何と言ってもコンサルタントの専門性の高さです。
一般の転職エージェントと違い、障がい特性に配慮した就職支援を専門に行っているため、初めての転職や再就職を目指す方でも安心して相談できます。
「どう伝えればよいか分からない」「自分に合った職場が見つかるか不安」といった気持ちにも丁寧に寄り添い、無理なく前に進めるようサポートしてくれるのが特徴です。
医療や障がい特性への理解が深い
dodaチャレンジのコンサルタントは、医療や障害に関する専門知識を備えており、精神障害、発達障害、身体障害などそれぞれの特性に応じた対応が可能です。
症状や配慮が必要な点についてもしっかり理解してくれるので、「安心して本音を話せた」「他の転職エージェントより理解が深かった」と感じた利用者が多くいます。
体調に波がある方や通院を続けながら働きたい方にも、働きやすい職場環境を一緒に考えてくれるのが強みです。
「配慮事項」や「働き方」など、細やかにヒアリングしてくれる
一般的な転職支援では見落とされがちな「配慮事項」や「働き方の希望」について、dodaチャレンジでは初回の面談から丁寧にヒアリングしてくれます。
「静かな職場がいい」「定期的な休憩が必要」「通院がある」など、生活スタイルや体調に合わせた条件をしっかり伝えることができ、紹介される求人もより自分にマッチしたものになります。
「この条件じゃ働けないのでは…」と不安に思うようなことも、きちんと受け止めてくれるため、就職活動へのハードルがグッと下がります。
希望を一方的に押し付けることはなく、「何が最適か」を一緒に考えてくれる姿勢に安心感を覚えるという声が多いです。
「障がい者雇用枠」の求人にありがちな「単純作業」ばかりじゃなく、スキルや希望にマッチした求人を紹介してくれる
「障がい者雇用=単純作業ばかり」というイメージを持っている方も多いですが、dodaチャレンジではそのような固定観念にとらわれず、本人のスキルや経験、希望に合わせて多様な職種を紹介してくれます。
事務、経理、デザイン、エンジニア、マーケティングなど、キャリアアップを目指せる求人も多く、選択肢が豊富です。
「もっとやりがいのある仕事がしたい」「これまでの経験を活かしたい」という思いにもしっかり応えてくれるため、「ただ働ければいい」ではなく、「納得のいく就職」が目指せるのが魅力です。
実際にdodaチャレンジを利用して転職した方からは、「希望通りの働き方が叶った」「スキルアップにつながった」といった前向きな口コミが多く寄せられています。
特徴2・大手パーソルグループのネットワークを活かしてるから、求人の数と幅が他とはレベル違い
dodaチャレンジは、国内でもトップクラスの人材サービスを展開する「パーソルグループ」によって運営されています。
そのため、求人の数と種類が非常に豊富で、他の障害者向け就労支援サービスと比べてもそのスケール感は別格です。
一般的な事務職や軽作業に限らず、IT系・専門職・管理部門など多岐にわたる求人が揃っており、「自分に合った仕事が見つからない」と感じていた人にとっては、新たな可能性を広げてくれるサービスです。
さらに、パーソルグループは多くの企業と深い信頼関係を築いており、他では公開されていない求人情報も多く取り扱っています。
そのため、表に出ていないチャンスに出会える可能性も高く、「他では紹介されなかった求人に巡り合えた」といった口コミも少なくありません。
就職の選択肢を広げたい方にとって、dodaチャレンジは非常に魅力的な選択肢と言えるでしょう。
大手優良企業の非公開求人が多い
dodaチャレンジの強みのひとつが、「非公開求人」の多さです。
これは、企業が採用戦略上、一般には公開せずに信頼できる紹介会社にだけ任せる求人のこと。
dodaチャレンジでは、こうした大手優良企業の非公開求人を数多く保有しており、希望条件にマッチする案件をピンポイントで紹介してもらえるのが大きな魅力です。
実際に「自分では探せなかったような求人を紹介してもらえた」「大手企業で安定した働き方ができるようになった」という声も多く、他サービスと比較して求人の“質”に満足している利用者が目立ちます。
職種や勤務地、働き方にこだわりがある方にとって、こうした選択肢の広さは大きな武器になります。
特徴3・入社後のフォローもしっかりやってくれるから職場定着率支援が手厚い
dodaチャレンジの魅力は、就職が決まった“後”にも続きます。
多くの転職サービスが「内定=ゴール」とする中で、dodaチャレンジは就職後のサポートに特に力を入れており、これが高い職場定着率にもつながっています。
仕事が始まったばかりの頃は、慣れない環境や人間関係で不安が募ることもありますが、dodaチャレンジではそんな時にすぐ相談できる体制が整っているため、「一人じゃない」と感じながら働き続けることができます。
さらに、定着支援の一環として、企業側との調整やアドバイスなども積極的に行ってくれるため、職場に直接言いにくいことがある場合も、安心して相談できます。
安心して長く働ける環境づくりにまでしっかり寄り添ってくれるのが、他サービスにはない大きな魅力です。
「こんなこと言って大丈夫かな?」という悩みも、コンサルタントが代わりに企業に伝えてくれることもある
職場での人間関係や業務内容の悩みなど、「直接伝えるのが難しい」「トラブルにならないか不安」と感じることってありますよね。
dodaチャレンジでは、そういった繊細な問題にも丁寧に対応してくれる体制が整っており、必要に応じてコンサルタントが企業と連携してくれることもあります。
「こんなこと言っていいのかな…」とためらってしまうようなことでも、第三者の立場から冷静かつ丁寧に伝えてもらえることで、状況がスムーズに改善されたというケースも多いです。
コンサルタントがしっかり味方になってくれることで、安心して働き続けられる環境が整うのは、大きな安心材料です。
定着率が高いのは就職後のフォローの手厚さのおかげ
dodaチャレンジの定着率の高さは、入社後も継続して寄り添うサポート体制に支えられています。
就職が決まってから数か月、場合によっては半年〜1年にわたり、定期的な面談や職場でのヒアリングなどを通じて、継続的な支援が行われています。
その結果、「働き始めたあとも不安を感じることなく過ごせた」「誰かに見守ってもらえている安心感があった」といった口コミが多く寄せられています。
一度就職したものの早期退職してしまった経験がある方にとっても、このアフターフォローの手厚さは非常に心強く、「今回は長く働けそう」と前向きに感じられる支えになります。
単なる紹介で終わらず、働き続ける未来まで見据えて支援してくれるからこそ、定着率の高さという結果にもつながっているのです。
特徴4・対応エリアは全国!対応スピードも早い。地方在住でもフルリモートの仕事を提案してくれる
dodaチャレンジの魅力は、東京や大阪など都市部だけでなく、地方に住んでいる方にも平等にチャンスがあることです。
オンライン面談やリモート支援に対応しているため、近くに支援機関がなくても、電話やZoomなどでコンサルタントとやり取りが可能です。
地方在住で通勤が難しい方にも、フルリモートや在宅勤務が可能な求人を紹介してくれるので、「地元を離れずに働きたい」「家庭の事情で引っ越せない」といった方にもぴったりです。
さらに、対応のスピード感も高評価ポイント。
登録後すぐに連絡があり、ヒアリングから求人紹介までの流れがスムーズです。
「待たされることなく動き出せた」「タイミングを逃さず転職できた」という口コミも多く、転職市場の変化が激しい中で、この“即対応力”は非常に頼りになるといえます。
登録から求人紹介までが早い!タイムリーな対応でチャンスを逃さない
転職活動では「タイミング」がとても重要です。
良い求人があっても、対応が遅れれば他の応募者に先を越されてしまうことも。
dodaチャレンジでは、その心配がほとんどありません。
登録後すぐに担当者から連絡が入り、ヒアリング、求人提案までがとにかくスピーディー。
早ければ登録から数日以内に求人の案内が届くケースもあります。
このスピード感に助けられたという声も多く、「退職を決めてから1か月以内に次の職場が決まった」「在職中でも効率よく転職活動が進められた」といった満足度の高い体験談も見られます。
“すぐに動きたい”というタイミングを逃さないサポートが、dodaチャレンジの大きな強みです。
特徴5・障がい者雇用でもキャリアアップを目指せる
多くの障がい者雇用の求人は、「補助的な業務」や「簡単な作業」に偏りがちですが、dodaチャレンジでは「その人のスキルを活かし、キャリアアップを目指せる仕事」を前提に求人提案を行ってくれます。
本人の経験や得意分野を丁寧にヒアリングし、それに見合ったポジションや将来的に成長できる環境を提案してくれるため、ただの“就職”にとどまらない支援が受けられます。
これまでに「障がい者雇用だから我慢するしかない」と感じていた方でも、スキルを活かした働き方や役職のあるポジションを提案されることも珍しくありません。
「希望ややりがいを持って働きたい」と思う方にこそ、dodaチャレンジはおすすめです。
dodaチャレンジは「キャリアアップ前提」での転職サポートが得意
他の転職支援サービスと異なる点として、dodaチャレンジは最初から「キャリアアップ」をゴールに見据えた支援を行っています。
「障がいがあるから」といって業務の幅を制限せず、過去の経験やスキルを活かした職場を紹介してくれるため、「次のステップを目指せる転職」が実現しやすいです。
コンサルタント自身も、単なる職探しではなく「今後どうなりたいか」「キャリアとして何を築きたいか」といった未来志向の視点で相談に乗ってくれるため、納得感のある転職がしやすいのも特徴です。
スキルを活かしたポジションや、役職付きの案件も豊富
dodaチャレンジでは、実務経験を積んできた方に向けた「専門スキルを活かせる求人」や、「管理職・リーダー候補」として採用される求人も多く取り扱っています。
これまでに培ったスキルを正当に評価してもらえる環境を見つけたい方にとって、希望に合う案件が見つかりやすいのが魅力です。
実際に「部下を持つ立場で転職できた」「前職より条件が上がった」といった声もあり、障がい者雇用だからといってキャリアを諦める必要がないことを体現しています。
「ただ働く」のではなく「成長を続けたい」人にこそ、dodaチャレンジはぴったりのサービスです。
dodaチャレンジの口コミは?dodaチャレンジのメリットや他の就活サービスより優れているポイントは?
「就活サービスってどれを選べばいいの?」と悩む方は多いですが、dodaチャレンジはその中でも特に“ミスマッチの少なさ”や“選べる求人の幅広さ”で好評を集めています。
障がいのある方のために設計された専門サービスだからこそ、一般的な転職サイトでは得られないような、細やかで現実的な支援を受けることができるのが特徴です。
ここでは、dodaチャレンジが他の就職支援サービスと比べて、どんな点で優れているのかを具体的に比較しながら解説していきます。
dodaチャレンジと他の就活サービスのメリットを比較
dodaチャレンジは、「転職エージェント+障がい特化」のハイブリッド型サービスとも言える存在です。
他の支援機関や求人サイトと比べて、どのようなメリットがあるのか、実際の利用者の声をもとに確認していきましょう。
メリット1・障害の種類や特性に配慮したアドバイスをくれるからミスマッチが少ない
多くの就職支援サービスでは、障害の有無に関係なく同じアプローチを取ることがありますが、dodaチャレンジでは違います。
発達障害、精神障害、身体障害、内部障害など、障害の種類や特性ごとに専門知識を持ったコンサルタントが対応してくれるため、希望条件だけでなく「配慮が必要な点」までしっかりヒアリングしてくれます。
その結果、「入社してから環境が合わなかった」というミスマッチが起こりにくく、実際に「職場の人間関係が楽になった」「働きやすさを実感している」といった声が多く寄せられています。
障がいについて話しづらいと感じている方にも、安心して相談できる環境が整っているのが大きな安心ポイントです。
メリット2・公開求人が中心で在宅勤務・時短勤務など柔軟な提案をしてくれる求人が豊富
dodaチャレンジでは、求人情報の透明性が高く、基本的に「公開求人」が中心です。
これにより、「どんな企業なのか」「業務内容はどうか」といった情報を事前にしっかり確認できるため、不安を減らして転職活動に臨むことができます。
さらに、リモートワーク可能、時短勤務、週3〜4日勤務OKなど、働き方に柔軟性のある求人が多いのも魅力のひとつです。
特に体調の波がある方や、家庭と仕事の両立を目指したい方にとって、こうした柔軟な働き方が選べる環境は非常にありがたいもの。
「通勤に不安があるけれど働きたい」「自分のペースで無理なく働きたい」という方にとって、dodaチャレンジの求人の質とバリエーションの多さは、大きな武器になるはずです。
メリット3・転職後のフォローアップ面接や相談を続けてくれる
dodaチャレンジの大きな特長のひとつは、就職がゴールではなく「定着」がゴールだと考えている点です。
就職後も専任のコンサルタントが定期的にフォローアップ面談を実施しており、職場での悩みや環境への不安を気軽に相談できる体制が整っています。
「入社して終わりではない」というスタンスがあるからこそ、安心して長期的なキャリア形成に取り組むことができます。
特に、就職してから数週間〜数ヶ月は新しい環境に慣れるまで時間がかかることも多く、不安やストレスを抱えやすい時期です。
そんなときに、外部の相談相手として信頼できるコンサルタントが寄り添ってくれることで、「自分だけじゃない」と感じられ、心の支えになるという声が多く寄せられています。
メリット4・スキルを活かせるポジションが多数ある・キャリアアップや年収アップの可能性がある
「障がい者雇用=単純作業」ではない、という価値観を体現しているのがdodaチャレンジです。
これまでに培ったスキルや経験を活かしたポジションの求人が多数あり、たとえば経理、総務、エンジニア、Webデザイナー、マーケティング職など、専門性の高い職種での転職実績も豊富です。
本人の希望や適性に合わせて、キャリアアップを目指せる転職を後押ししてくれます。
また、一般的に「障がい者雇用は待遇が下がる」と言われがちですが、dodaチャレンジでは年収アップを実現したケースも珍しくありません。
企業との条件交渉もコンサルタントが代行してくれるため、「待遇面が不安」という方でも安心して相談できます。
一歩踏み出せば、思わぬキャリアチャンスが広がっていることもあります。
メリット5・オンライン面談や電話相談が充実しているから地方在住でも手厚くサポートしてもらえる
dodaチャレンジでは、オンライン面談・電話相談を基本対応としているため、全国どこに住んでいても等しくサポートを受けられるのが魅力です。
地方に住んでいると、「都市部と比べて求人が少ない」「支援サービスが限られている」と感じる方も多いですが、dodaチャレンジなら自宅にいながら希望に合った求人を紹介してもらうことが可能です。
また、地方在住者向けに在宅勤務やリモートワーク対応の求人も豊富に取り扱っているため、「地元を離れずに働きたい」「通勤が難しいけれど働きたい」という方にもぴったりです。
ヒアリングや面接対策、条件交渉などもすべてオンラインで完結できるため、スムーズに転職活動を進められます。
地方にいても都市部並みの支援が受けられる、それがdodaチャレンジの大きな強みです。
dodaチャレンジの口コミやデメリットについて調査しました
dodaチャレンジは、障がいのある方の転職支援に特化したサービスとして高く評価されていますが、すべての人にとって最適なサービスというわけではありません。
どんなに優れたサービスにも、向き不向きや課題となる点は存在します。
ここでは、実際の利用者の声や比較情報をもとに、dodaチャレンジのデメリットや注意点について詳しく解説します。
デメリット1・新卒・第二新卒・既卒向けのサポートが少ない
dodaチャレンジは、転職経験のある方向けの支援に強みを持っており、すでに社会人経験がある方や再就職を目指す方には非常に心強いサービスです。
しかし一方で、「これから初めて社会に出る」という新卒・第二新卒・既卒者向けのサポートはやや弱い傾向があります。
たとえば、就活で必要な自己分析、エントリーシート(ES)の書き方、面接練習など、「就職活動そのものが初めて」という方には少し不安が残る部分もあるようです。
もちろん相談には乗ってくれますが、そうしたノウハウを手取り足取り教えてくれるスタイルではないため、新卒層にはやや不向きと感じるケースもあるようです。
「就活エージェント」系は、新卒のための面接対策やES添削などが手厚い
新卒の方や大学を卒業して間もない方には、dodaチャレンジよりも「就活エージェント」系のサービスの方が相性がいいこともあります。
就活エージェントは、新卒の支援を専門にしているため、履歴書やエントリーシートの添削、模擬面接の実施、企業とのマッチングまで、手厚いサポートを受けることが可能です。
特に「面接の経験が全くない」「就職活動の進め方がわからない」という方にとっては、こうしたサービスの方が安心感を持って取り組めることも多いです。
dodaチャレンジは中途向けに設計されたサービスであるため、どうしても“転職前提”の内容に偏りがちです。
「就活エージェント」系は、就活初心者にはピッタリのサービスが多い
社会経験が少ない方にとって、最初の就活は不安や戸惑いがつきものです。
そんなときは、新卒・既卒専門の就活エージェントを利用することで、ゼロから丁寧に就活の流れを教えてもらえるメリットがあります。
企業選びのポイントから自己PRの作り方まで、徹底的にサポートしてくれるサービスが揃っているため、「何をすればいいかわからない」という状態でも安心して進めることができます。
もちろん、障がいをお持ちの方でも新卒枠で利用できる就活エージェントは存在するので、「まずは働く経験を積みたい」「ステップアップはその後に考えたい」という方には、dodaチャレンジよりも適した選択肢が見つかるかもしれません。
デメリット2・インターンや合同説明会のイベントが少ない
dodaチャレンジでは、個別のキャリア相談や求人紹介は非常に充実していますが、就活イベントや合同企業説明会、インターンシップといった“広く情報を集められる場”はそれほど多くありません。
企業の雰囲気を知ったり、他の求職者との情報交換をしたりするチャンスが限られるという点は、特に就活初期段階の方にとっては少し物足りなさを感じることもあるかもしれません。
一方で、「一対一でじっくり話したい」「大勢の中での説明会は疲れてしまう」といった方には、静かな環境で落ち着いて相談できるdodaチャレンジのスタイルが合うこともあります。
ただし、情報収集の量やスピードを重視する場合には、就活エージェント系のイベント活用を併用するのもおすすめです。
「就活エージェント」系は、大規模な合同説明会やオンラインフェアに参加できるから、情報収集が早い
新卒や既卒の就活支援に強いエージェントでは、合同説明会やオンライン就活フェアを頻繁に開催しており、1日で数十社の企業情報を得られる機会もあります。
企業の採用担当者が直接プレゼンを行ったり、仕事内容を詳しく紹介してくれるため、情報収集のスピードが格段にアップします。
これにより、「まだ業界を絞れていない」「広く選択肢を見たい」という段階の方にとっては、大きなメリットとなります。
複数の企業を比較しながら、進路を固めていきたい方には、こうした機会を活用できるエージェント型サービスが相性が良いでしょう。
「就活エージェント」系は、企業の担当者と直接話せる機会がある
もうひとつの大きなメリットは、企業の採用担当者と直接会話できる機会があることです。
就活イベントや説明会の場では、「どんな人材を求めているのか」「実際の働き方はどうなのか」といったリアルな情報を直接聞くことができ、企業との距離がぐっと縮まります。
このような“生の声”を聞けることは、求人票だけではわからない空気感や職場環境を知るために非常に有効で、「思っていた職場と違った」というミスマッチを防ぐ手助けにもなります。
dodaチャレンジはマンツーマンでの支援には強いですが、こうした“広く浅く知る”場面では就活エージェントの方が得意といえるでしょう。
デメリット3・対象業界の幅が狭い
dodaチャレンジが扱っている求人は、障がい者雇用枠が中心となるため、職種としては事務系・軽作業・ITサポートなどが多く、どうしても対象業界が限られてくる傾向があります。
たとえば「商社で営業がしたい」「広告代理店で働きたい」といった希望を持っている方にとっては、希望通りの求人が少なく、満足のいく選択肢が得られない可能性もあります。
もちろん、スキルや経験に応じた求人紹介は受けられますが、「業界へのこだわりが強い」場合は、一般枠も視野に入れられる就活エージェント系の方が向いているかもしれません。
dodaチャレンジは、“働きやすさ”や“長く続けられる環境”を重視する人にはとても心強いですが、業界重視で攻めたい方にはやや不向きな面もあります。
「就活エージェント」系は、IT、商社、広告など、「一般枠」での採用が基本なので対象業界が幅広い
就活エージェント系のサービスは、いわゆる「一般枠」の求人を扱っているため、業界の幅がとても広いのが特徴です。
IT、商社、金融、広告、マスコミなど、就活生に人気の業界にも幅広く対応しており、企業研究や業界分析をしながら自分に合った職場を探していくことが可能です。
そのため、「入りたい業界が明確に決まっている」「特定業界の仕事にこだわりたい」という方にとっては、dodaチャレンジよりもエージェント型サービスの方が適しているケースもあります。
自分のキャリア観や優先順位に合わせて選ぶことが大切です。
「就活エージェント」系は、自分の興味ある業界にこだわりたい人には強い味方になる
就活エージェント系のサービスでは、業界ごとの専門アドバイザーが在籍していることも多く、たとえば「IT業界志望ならこの人」「マスコミ業界を目指すならこの担当」といった形で、より深い業界知識を持ったアドバイスが受けられます。
これにより、自己PRや志望動機の作成、面接対策まで、業界に特化したサポートを受けることが可能になります。
そのため、「この業界じゃなきゃイヤ!」「専門性を高めたい!」という強いこだわりを持っている人にとっては、就活エージェント系はまさに頼れる味方です。
dodaチャレンジもサポート体制は優秀ですが、業界特化の深さという面では、目的によって使い分けるのがベストです。
デメリット4・求人数が少ない
dodaチャレンジは障がい者雇用に特化したサービスであるため、求人の質は高いものの、絶対的な「数」で見ると一般向けの転職サイトに比べて少なめです。
特に「選択肢をたくさん見て比べたい」「幅広い業種・職種から選びたい」といった希望を持つ方にとっては、物足りなさを感じる場面もあるかもしれません。
また、エリアによっては求人が集中している地域とそうでない地域の差があるため、地方在住の方は特に選択肢が限られる傾向があります。
もちろん、在宅勤務やリモートワークの求人もありますが、通勤前提の案件に比べると選択肢が少ないのが現状です。
求人の数そのものを重視したい場合は、複数のサービスを併用するのが安心です。
リクナビ、マイナビ、エン転職などは、登録企業数が数万社規模
大手求人サイトであるリクナビNEXT、マイナビ転職、エン転職などは、登録企業数が圧倒的に多く、数万社規模の情報が日々更新されています。
職種、業界、雇用形態、勤務地など、あらゆる条件から検索できるため、「とにかくたくさんの求人を見て比べたい」という方には向いています。
その反面、障がい者への配慮がどこまであるかは企業によって異なるため、自分で確認したり、交渉したりする負担が発生する可能性も。
情報の多さは魅力ですが、自分に合う職場を見極める力が求められる点では、dodaチャレンジのような専門支援サービスとは使い方が異なるといえるでしょう。
未経験からチャレンジできる案件が少ない
dodaチャレンジでは、「これまでの経験やスキルを活かした仕事」をベースに求人を紹介する傾向が強いため、まったくの未経験分野にチャレンジしたいという場合、選択肢が限られてしまうことがあります。
もちろん、未経験OKの求人も取り扱いはありますが、全体の中では比率がそれほど高くないのが現状です。
そのため、「職歴ゼロでこれから初めて働く」「完全に異業種へ転職したい」という方にとっては、少しハードルを感じるかもしれません。
特にスキルや経験に自信がない場合は、未経験者歓迎の案件が豊富な別サービスを併用することで、より自分に合った道が開ける可能性があります。
「就活エージェント」系は、新卒・第二新卒枠を利用すれば、職歴ゼロでもOKな求人が多い
新卒や第二新卒を対象にしている就活エージェントでは、職歴や実務経験がなくても応募可能な求人が数多く取り扱われています。
研修制度が整った企業や、「ポテンシャル採用」を重視する企業が中心のため、社会人経験が浅い方でも安心してスタートできる環境が整っています。
「今までアルバイト経験しかない」「卒業後にブランクがある」といった不安を抱えている方でも、面接対策や履歴書の書き方などを丁寧にサポートしてくれるため、無理なく就職活動が進められます。
未経験からのチャレンジを本気で応援してくれるのは、就活エージェント系ならではの強みです。
dodaチャレンジの口コミはどう?dodaチャレンジのサービスを実際に利用した人の口コミ・評判は?
実際にdodaチャレンジを利用した方々の口コミには、具体的な体験に基づいた感想が多く寄せられています。
ここでは、利用者の生の声をもとに、サービスのどんな点が評価されているのかをご紹介します。
安心して転職活動を進めたい方には、非常に参考になる内容ばかりです。
良い口コミ1・面談では『どんな配慮があると働きやすいですか?』って具体的に聞いてくれて、企業にもそのまま伝えてくれたので、面接でも安心して話せました。
この口コミは、dodaチャレンジの「ヒアリング力」と「企業との橋渡し能力」の高さを物語っています。
単に求人を紹介するだけでなく、本人の働きやすさを第一に考えた配慮事項を細かくヒアリングしてくれるため、「どんな職場なら自分らしく働けるか」が明確になります。
その内容をそのまま企業側にしっかり伝えてくれることで、面接の段階から安心して話せる空気が生まれ、結果的に内定にもつながりやすくなります。
「自分でうまく説明できるか不安…」という方には特に心強いサポートです。
良い口コミ2・事務職ばかりかと思ったら、IT系のエンジニア職や専門職の求人もたくさん紹介されました。しかも、大手企業の求人もあって驚きました
「障がい者雇用=単純作業」というイメージを持っている方にとって、この口コミは驚きかもしれません。
dodaチャレンジでは、事務職だけでなく、ITエンジニア、Web制作、経理、総務、法務など、専門性の高い職種も豊富に取り扱っています。
また、大手企業とのパイプも強く、非公開求人や上場企業のポジションも提案されることがあります。
スキルや経験を活かした働き方を目指している方には、非常に魅力的な環境が整っていると言えるでしょう。
良い口コミ3・転職した後も、月1回のペースでフォロー面談があって、悩みを聞いてくれました。自分では言いづらい職場の困りごとも、担当者がうまく伝えて調整してくれて、とても助かりました
就職して終わりではなく、就職“後”のサポートまで継続してくれるのが、dodaチャレンジの大きな強みです。
フォロー面談を通じて、職場での悩みや不安を相談できる機会が定期的に設けられているため、「問題が大きくなる前に解決できた」と感じる方が多いです。
特に、職場に直接言いにくいことを第三者が代わりに伝えてくれる体制は、精神的な負担を大きく軽減してくれます。
定着支援に力を入れているからこそ、長く働き続けたい方に選ばれています。
良い口コミ4・私は東北在住ですが、オンライン面談でスムーズにサポートしてもらえました。リモートワークOKの求人も紹介されて、地方でも選択肢があるんだと感じました
dodaチャレンジは、全国対応型のサービスで、地方に住んでいる方でもオンラインでしっかりサポートが受けられます。
Zoomなどのビデオ通話を活用して、ヒアリングや求人紹介、面接対策まで丁寧に行ってくれるため、都市部に行かずとも転職活動が完結するのが特徴です。
また、在宅勤務やフルリモートの求人も扱っているため、「通勤が難しい」「地元から離れたくない」といったニーズにも柔軟に対応可能です。
地方在住者にとって、安心感と選択肢の多さは大きなメリットになります。
良い口コミ5・障害者雇用だと単純作業ばかりと思っていましたが、スキルアップやキャリアアップも考えて求人を探してくれました。
dodaチャレンジは、障がい者雇用=制限された働き方という考えを覆してくれるサービスです。
利用者のスキルや希望に応じて、「今できる仕事」だけでなく「今後挑戦したいこと」や「キャリアとして伸ばしたい方向性」まで見据えた提案をしてくれます。
そのため、「ただ働く」だけでなく、「成長しながら働きたい」「もっと上を目指したい」と考える方にもぴったり。
実際に、昇給やキャリアチェンジにつながったという事例もあり、障がいがあっても前向きに未来を描ける支援体制が整っています。
悪い口コミ1・担当者によっては、障害への理解があまり深くないと感じたことがあります。『もっと詳しく説明しないといけないの?』と不安になりました
dodaチャレンジの担当者は基本的に障がい者支援に特化したトレーニングを受けていますが、それでも担当者ごとに「経験値の差」があるのは事実です。
特に、症状の説明や配慮の希望について深く理解してもらえないと、利用者側は「自分で説明を全部しなければならない」と感じてしまい、負担に思うこともあるようです。
これはどの支援サービスにも起こりうる課題ですが、対策としては「担当変更の相談を早めにする」ことが有効です。
実際に、担当を変えてもらったことでスムーズにやり取りできたという声もあるので、不満を感じたら遠慮せず申し出ることが大切です。
悪い口コミ2・事務系やIT系以外の職種が少ない印象を受けました。もう少しクリエイティブ系や他業種の求人も増えたらいいなと思います
dodaチャレンジの求人は、障がい者雇用に特化している関係で、どうしても「安定性の高い職種」が中心になります。
そのため、一般事務やITサポート、軽作業といったジャンルが豊富にある一方で、デザイン、ライティング、広告、アパレルなど、いわゆるクリエイティブ職や業界特化型の求人はやや少なめです。
自分の専門分野や希望業界が明確にある場合は、dodaチャレンジだけでなく、業界特化型の転職エージェントや、一般求人サイトと併用するのがおすすめです。
キャリアの方向性が定まっている方ほど、複数の視点から求人を見られる環境を整えると安心です。
悪い口コミ3・フォローはあると言われたのですが、転職後こちらから連絡しないと音沙汰がなかった…。自分から積極的に連絡を取る必要があるなと感じました
dodaチャレンジでは就職後のフォロー体制が整っているとされていますが、実際には担当者の対応にばらつきがあるとの声もあります。
中には「こちらから連絡しないとフォロー面談がなかった」「定期連絡は最初だけだった」という口コミもあり、期待していた手厚いサポートが受けられなかったと感じるケースもあるようです。
もちろん、自主的に連絡を取れば対応してもらえることがほとんどですが、「言い出しにくい」「サポートが受けられると思っていた」というギャップを感じた方にとっては不安材料になります。
不安がある場合は、事前にフォローの頻度や方法について確認しておくことが大切です。
悪い口コミ4・地方在住ですが、リモートOKの求人は少なく、結局関東や関西の案件が多かったです。地元企業の求人はあまり見つかりませんでした
dodaチャレンジは全国対応のサービスですが、求人のボリュームに関してはやはり都市部に集中しているのが実情です。
特にリモートワークOKの求人は首都圏を拠点とする企業が中心で、地方企業からの求人は全体に対して少なめ。
結果的に、「希望する勤務地で求人が見つからない」と感じた方もいるようです。
地方在住の方がフルリモートで働くには、IT系など在宅対応しやすい職種を中心に探す必要がありますが、その分選択肢が狭まることは否めません。
地元での就職を希望する場合は、ハローワークや地域密着型の支援機関との併用も検討するとよいでしょう。
悪い口コミ5・キャリアアップを目指したいと思っても、スキルや経験が不足していると難しい求人が多かったです。未経験者向けのキャリア支援ももっとあればいいのに、と思いました。
dodaチャレンジは、スキルや経験を活かしてキャリアアップを狙う方に強い一方で、「これからスキルをつけたい」「未経験から始めたい」という方にとっては、ややハードルが高く感じる場面もあるようです。
求人の中には、一定の実務経験やスキルを前提としているものが多く、「最初の一歩」としては厳しいという声も見られました。
特に、新卒や第二新卒、ブランクが長い方にとっては「選べる求人が少ない」と感じることもあります。
こうした場合は、未経験可の研修付き求人が充実している就活エージェント系や、スキル習得を前提としたスクール型支援サービスを併用するのも有効です。
dodaチャレンジの口コミはどう?内定率・採用率はどう?求人が多い職種について
転職活動を進める上で気になるのが「本当に内定がもらえるのか」という点です。
dodaチャレンジは、障がいのある方向けの専門的な転職支援サービスでありながら、内定率が高いと評判です。
ここでは、実際の内定率やその理由、さらに求人が多い職種について詳しく解説していきます。
dodaチャレンジ【公開求人】の内定率について/内定率は約60~70%
dodaチャレンジでは、公式にも内定率は60〜70%と公表されています。
これは、他の転職支援サービスや一般的な就職活動と比べてもかなり高い水準です。
なぜここまで高い内定率を実現できているのか——その背景には、dodaチャレンジならではのサポート体制と、マッチング精度の高さがあります。
利用者の声を見ても、「初めての転職だったがスムーズに内定まで進めた」「他社では難しかったが、ここでは話が早かった」といった満足度の高い口コミが多数見られます。
内定率が高い理由1・専門のキャリアアドバイザーがミスマッチを減らす
dodaチャレンジでは、障がいのある方の支援に特化したキャリアアドバイザーが一人ひとりの状況を丁寧にヒアリングし、最適な求人を紹介してくれます。
そのため、「応募したけど職場環境が合わなかった」「面接で配慮が伝わらず落ちてしまった」といったミスマッチが起こりにくいのが特徴です。
さらに、配慮事項や体調に関する希望など、就職活動では伝えにくいことも代弁してくれるので、面接の時点で相互理解が深まりやすく、採用にもつながりやすくなります。
マッチング精度の高さが、内定率アップの大きな要因となっています。
内定率が高い理由2・求人の質が高く、企業側も障がいへの理解がある
dodaチャレンジが取り扱う求人は、あらかじめ障がい者雇用に理解のある企業ばかり。
これは、dodaチャレンジが長年培ってきた企業ネットワークと、採用担当者への事前ヒアリングにより、企業の受け入れ体制や配慮内容をしっかり把握しているからです。
そのため、利用者は「無理をせず働ける環境」での求人を安心して選ぶことができ、企業側も「理解ある採用」が前提となっているため、選考もスムーズに進みやすくなります。
安心して働ける職場を前提とした求人ばかりなので、早期退職のリスクも少なく、企業・求職者ともにwin-winの関係を築きやすいのがポイントです。
内定率が高い理由3・面接前の準備・アドバイスが丁寧で、企業との条件調整もしてくれる
面接対策がしっかりしていることも、dodaチャレンジの内定率の高さを支える大きな要素です。
自己PRの作り方や志望動機の伝え方、配慮事項の説明方法など、面接前には丁寧なアドバイスとロールプレイを通じて準備が進められます。
また、企業との間に立って、就労条件や配慮が必要な点について交渉・調整をしてくれるため、利用者は「面接で全部自分で説明しなきゃ…」というプレッシャーから解放されます。
こうした事前準備の手厚さと、担当者の丁寧な対応が安心感につながり、自信を持って選考に臨めることが、内定率の高さに直結しています。
dodaチャレンジ【紹介求人からの内定率】の採用率について/採用率は約20~30%
dodaチャレンジでの紹介求人からの内定率は、おおよそ20~30%となっています。
この数字は、障がい者雇用を対象とした他の転職サービスと比較しても、かなり高めです。
一般的に障がい者向け求人の採用率は10~15%前後と言われているため、dodaチャレンジの実績は非常に優秀といえるでしょう。
その理由のひとつは、求人紹介の段階で「ミスマッチ」を徹底的に排除している点です。
求職者の希望条件や障がい特性を細かくヒアリングしたうえで、企業側とも事前にしっかり情報共有してから面接へ進むため、双方の理解がスムーズで、選考も前向きに進みやすくなります。
通常の障がい者転職サービスの採用率よりも高い
他の障がい者向け転職サービスでは、応募数が多くても採用に結びつかないケースが少なくありません。
その一因として、配慮事項の伝達不足や、企業との条件面のすり合わせの弱さが挙げられます。
dodaチャレンジでは、こうしたポイントを事前にカバーし、応募者と企業の間に立って丁寧に調整を行ってくれるため、結果的に採用率が高まっています。
また、企業側にとってもdodaチャレンジは信頼できる採用パートナーとなっているため、「受け入れ準備が整っている企業」が集まりやすいのも特徴です。
だからこそ、他社と比べて採用決定率が高くなるのです。
dodaチャレンジ【未経験OK求人】の内定率について/内定率は40~50%
dodaチャレンジは、経験者向けの求人だけでなく、「未経験OK」の求人も多数取り扱っています。
そして驚くべきことに、その未経験者向け求人における内定率は40〜50%と非常に高水準です。
「未経験で不安…」という方でも、しっかり準備すれば結果が出やすいことがうかがえます。
未経験者向け求人には、基礎的なビジネススキルがあれば応募可能な職種が多く含まれており、特に事務補助、データ入力、サポート業務などが人気です。
dodaチャレンジでは、応募前に面談で不安点をしっかり解消し、書類の添削や面接対策もセットで実施してくれるため、初めての就職・転職にも安心して臨める環境が整っています。
書類添削や模擬面接をきちんと受けた人ほど、内定率が上がっている傾向あり
実際にデータとしても、dodaチャレンジで書類添削や模擬面接といった事前サポートをしっかり活用した方の方が、内定率が高い傾向にあります。
特に未経験の場合は、志望動機や自己PRをどう伝えるかが合否を左右するポイントになるため、プロの目線でアドバイスを受けることが非常に重要です。
模擬面接では、想定質問に答える練習を繰り返すだけでなく、「配慮事項の伝え方」や「体調への対応をどう説明するか」といった実践的な指導があるため、面接本番でも落ち着いて対応できたという声が多いです。
dodaチャレンジ【利用者の「職場定着率」】は90%以上
dodaチャレンジのもうひとつの特長は、「就職後に続けやすい職場」に出会えることです。
実際に、就職後の定着率は90%以上という驚きの実績があり、多くの利用者が長く安定して働き続けられていることが分かります。
これは、転職活動の段階から「長く働ける環境かどうか」を重視したマッチングを行っているためです。
業務内容だけでなく、人間関係や勤務体系、職場の雰囲気まで細かく確認し、無理のない働き方ができる求人を優先的に紹介しています。
だからこそ、「せっかく就職したのにすぐ辞めたくなる」といった事態が起きにくいのです。
転職後のフォロー体制やマッチングの精度が高いから定着率が高い
定着率の高さの裏には、dodaチャレンジの手厚いフォロー体制があります。
就職が決まったあとも、月1回のペースでフォロー面談が行われたり、困ったときにはすぐ相談できる窓口が用意されていたりと、「一人で抱え込まない環境」がしっかり整備されています。
さらに、マッチングの段階で「その職場で本当に働き続けられるか?」という視点を重視しているため、無理な紹介や押しつけが少なく、安心してスタートできるという声が多いです。
求職者・企業の双方にとって納得感のあるマッチングが、定着率の高さに直結しているのです。
dodaチャレンジと一般的な求人サービスを比較
dodaチャレンジは障がいのある方向けに特化した転職支援サービスで、一般的な求人サービスとはさまざまな点で違いがあります。
特に内定率や職場定着率に注目すると、その差は明確です。
ここでは、dodaチャレンジと一般的な求人サービスを複数の指標で比較しながら、どんな人にどちらのサービスが向いているのかを整理してみましょう。
dodaチャレンジは、求人の紹介前にしっかりとヒアリングを行い、配慮事項や希望条件を企業に正確に伝えてくれるため、内定までのプロセスが非常にスムーズです。
加えて、就職後のフォローも手厚く、安心して長く働ける体制が整っている点も大きな魅力です。
一方、一般的な求人サービスでは、求人の数や業界の幅広さはあるものの、障がいへの配慮や個別のサポート体制は限定的になりがちです。
自分の状態や目的に合わせて、どちらを使うかを選ぶことが大切です。
以下の表を参考に、自分に合ったサービスを見極めてみてください。
| 指標 | dodaチャレンジ | 一般的な求人サービス |
| 内定率 | 約60~70% | 約40~50% |
| 採用率 | 約20~30% | 約10~20% |
| 未経験からの内定率 | 約40~50% | 約30~40% |
| 職場定着率(半年~1年) | 90%以上 | 約60~70% |
dodaチャレンジの内定率アップのためのポイントを紹介します
dodaチャレンジを利用して内定を得るためには、ただ紹介された求人に応募するだけでなく、準備と工夫が重要です。
サポートが充実しているとはいえ、最大限に活かすためには「積極的な利用者側の姿勢」も求められます。
ここでは、実際に内定率を高めた方々の声をもとに、dodaチャレンジを最大限に活用するための4つのポイントをご紹介します。
これから利用を検討している方や、すでに登録済みでステップアップを目指している方にも役立つアドバイスです。
内定率アップのポイント1・キャリアアドバイザーに遠慮せずに苦手なことや希望の配慮などを具体的に伝えましょう
dodaチャレンジの強みは、障がいに対する理解が深いキャリアアドバイザーが、求職者一人ひとりの状況を理解しながらサポートしてくれる点です。
ただし、その力を引き出すには、こちら側からも「どこが苦手か」「どんなサポートがあれば働きやすいか」などを具体的に伝えることが大切です。
遠慮してあいまいな表現をしてしまうと、的確なサポートが受けづらくなり、ミスマッチにもつながりかねません。
「音に敏感で静かな環境がいい」「人前での発表が苦手」「週4日勤務が理想」といった、細かい内容でも気兼ねなく共有しましょう。
アドバイザーはあなたの“味方”です。
内定率アップのポイント2・dodaチャレンジの書類添削はかなり丁寧だから必ず何度もチェックを受けましょう
履歴書や職務経歴書は、第一印象を決める大事なツールです。
dodaチャレンジでは、専門のキャリアアドバイザーによる書類添削がとても丁寧で、応募企業ごとのポイントを押さえた内容に仕上げてもらえます。
自己流で書いたものと比べると、その完成度は歴然です。
特に「配慮事項の書き方」や「志望動機の伝え方」など、一般の転職サイトではアドバイスがもらいにくい内容も、しっかりフォローしてくれます。
一度添削を受けて終わりではなく、何度もブラッシュアップしていく姿勢が、最終的な内定率アップにつながります。
内定率アップのポイント3・模擬面接で「伝え方」を練習しましょう
面接での「伝え方」は、内容そのもの以上に重要な要素です。
dodaチャレンジでは、模擬面接の機会を活用することで、「緊張してうまく話せない」「配慮事項をどこまで伝えるべきかわからない」といった不安を解消できます。
模擬面接では、実際の面接に近い形式で練習ができ、フィードバックも具体的です。
「言葉が詰まりやすいときはこう切り返すといい」「この表現はポジティブに言い換えられる」といった細かい指導が受けられるため、自信を持って本番に臨めるようになります。
特に面接が苦手な方こそ、何度も練習する価値があります。
内定率アップのポイント4・第一志望だけ受けることはせず幅広くエントリーして比較しましょう
「この企業が良さそう!」と感じたとしても、第一志望だけに絞って応募するのはリスクが高く、チャンスを狭めてしまいます。
dodaチャレンジでは、複数の求人にエントリーすることが推奨されており、比較検討することでより自分に合った職場が見つかる可能性が高まります。
また、他の企業との選考を通じて、自分の希望や適性がより明確になるケースも少なくありません。
複数エントリーすることで、面接の経験値も上がり、自信を持って志望企業に臨むことができます。
最初からひとつに絞らず、視野を広げて行動することが、結果的に満足のいく転職につながります。
dodaチャレンジの内定率が高い理由について解説します
dodaチャレンジが他の障がい者向け就職支援サービスよりも高い内定率(60〜70%)を誇っているのは、偶然ではありません。
利用者一人ひとりへの丁寧な対応と、企業との信頼関係、ミスマッチを防ぐ工夫など、成功に導くための“仕組み”がしっかり整っているからこそ実現できているのです。
ここでは、その理由を3つのポイントに絞ってご紹介します。
内定率が高い理由1・企業側もdodaチャレンジから紹介された人なら安心と思っている(企業との信頼関係が強い)
dodaチャレンジは、長年にわたって障がい者雇用に取り組んできた実績があり、その過程で多くの企業との強固な信頼関係を築いてきました。
企業側にとっても「dodaチャレンジ経由の候補者=必要な情報がきちんと共有されていて、ミスマッチが少ない」という安心感があります。
また、採用担当者に対しても障がい理解や配慮方法についてのアドバイスが提供されることがあるため、「受け入れる側も準備がしやすい」という声も多いです。
この信頼関係があるからこそ、企業はdodaチャレンジからの応募者を前向きに検討しやすくなり、結果として内定率が高くなるのです。
内定率が高い理由2・事前の情報共有とヒアリングで、入社後のギャップが少ない(ミスマッチを徹底的に減らしている)
就職活動でよくある失敗の一つに「入社してから思っていた職場と違った」というミスマッチがあります。
しかしdodaチャレンジでは、事前のヒアリングで本人の希望や懸念点、働く上での配慮事項まで細かく聞き取ったうえで、企業にもその情報をしっかり伝えています。
さらに、企業からも職場環境や仕事内容、配慮可能な範囲について詳細な情報を得ており、応募者に事前に共有してくれるため、「知らなかった」が起きにくくなっています。
これにより、選考から入社後までのギャップを極力減らし、安心して働ける環境へとつながっているのです。
内定率が高い理由3・入社後もdodaチャレンジのサポートがあるため企業も積極的に採用しやすい
dodaチャレンジの大きな特徴のひとつは、内定がゴールではなく「職場に定着すること」を重視している点です。
入社後も月1回ペースの面談や随時相談が可能で、必要に応じて企業側への橋渡しも行ってくれるため、企業としても安心して採用に踏み切ることができます。
特に、「職場内で問題が起きたらどうしよう」「本人が困っても声に出せなかったら…」という企業側の不安を、第三者であるdodaチャレンジの存在がカバーしてくれるため、「サポートがあるから採用に前向きになれた」という事例も多くあります。
この“伴走型サポート”があることで、企業と求職者双方が安心して前に進めるのです。
dodaチャレンジの求人が多い職種/紹介される求人の特徴について
dodaチャレンジでは、求職者のスキルや希望に応じた幅広い求人を取り扱っており、特に障がい者雇用においても「選択肢の多さ」が大きな強みとなっています。
求人の多くは、公開されていない非公開求人で構成されており、大手企業や上場企業、優良中小企業からの案件も豊富です。
職種の幅も広く、一般的な事務職はもちろん、ITエンジニア、Webデザイナー、経理、人事、マーケティングなどの専門職までカバーしており、「自分の経験を活かして働きたい」という方にとって魅力的な内容が揃っています。
また、在宅勤務や時短勤務に対応した柔軟な働き方が可能な求人も多く、体調や生活スタイルに合わせた働き方を実現しやすい点も高評価です。
さらに、紹介される企業はすべて障がい者雇用に理解のある会社で構成されているため、「配慮事項をしっかり聞いてもらえた」「安心して面接に臨めた」という声も多く寄せられています。
自分に合った働き方やキャリアアップを目指すうえで、dodaチャレンジの求人の質と種類は大きな武器になると言えるでしょう。
| 【求人数が多い職種】
・非公開求人が多い(大手・優良企業多数!) |
dodaチャレンジの口コミは?dodaチャレンジの利用方法・登録方法について解説します
dodaチャレンジのサービスを利用するには、まず会員登録を行う必要がありますが、登録方法はとてもシンプルで数分程度で完了します。
登録後はキャリアアドバイザーとの面談を通して、自分に合った求人を紹介してもらう流れになります。
ここでは、dodaチャレンジの登録手順をわかりやすく2ステップに分けてご紹介します。
パソコンやスマートフォンからでも手軽に登録できますので、「まずは相談してみたい」という方にもぴったりです。
dodaチャレンジの登録方法1・dodaチャレンジ公式サイトへログイン/「会員登録する」をクリック
まずは、dodaチャレンジの公式サイトへアクセスします。
トップページには「会員登録する」というボタンがわかりやすく設置されているので、そこをクリックして登録画面へ進みましょう。
スマートフォンでも見やすく設計されているため、通勤中や休憩時間などのスキマ時間でも操作しやすいのが特徴です。
登録自体は無料で、転職相談や求人紹介などのサービスもすべて費用はかかりません。
特に、「いきなり応募は不安…」「どんな求人があるかだけ知りたい」という方でも、まずは会員登録だけして情報収集をするところから始められるので、気軽に利用できる仕組みになっています。
dodaチャレンジの登録方法2・基本情報を入力/入力後「登録する」をクリック
「会員登録する」ボタンをクリックすると、基本情報の入力画面に進みます。
入力項目は非常にシンプルで、初めての方でも迷うことなく進められます。
氏名、生年月日、都道府県、連絡先といった情報を記入したら、「登録する」ボタンを押すだけで完了です。
特に都道府県の入力に関しては、市区町村まで入れなくてもOKなので、個人情報の入力に不安がある方も安心して利用を開始できます。
登録が完了すると、後日キャリアアドバイザーから連絡が届き、希望の働き方や障がいに関する配慮事項についてヒアリングを受けるステップへと進みます。
| 【基本情報の項目】
– 氏名 |
dodaチャレンジの登録方法3・現在の状況についてチェックして登録
基本情報の入力を終えたら、次に「現在の状況」に関する簡単な質問に答えていきます。
これは、dodaチャレンジのキャリアアドバイザーが、あなたの今の状態を正確に把握し、より適した求人やサポートを提供するために欠かせないステップです。
決して堅苦しいものではなく、すべてチェック形式になっているので、時間もかからずスムーズに進めることができます。
例えば「今働いていますか?(在職中 or 離職中)」「どんな働き方を希望していますか?(在宅勤務・通勤・時短など)」「障がいの種類は?」といった項目に答えるだけで、担当者はその人に合った求人の傾向をつかみやすくなります。
これにより、マッチングの精度が格段に高まるのです。
登録時点での希望はあくまで「現時点での考え」でOKなので、途中で変更したい場合も気軽に相談できます。
正直に、そして無理のない範囲で回答することが、後悔のない転職活動への第一歩です。
| 【現在の状況についてチェック】
– 就業状況(在職中 or 離職中) |
dodaチャレンジの担当キャリアアドバイザーとの予約方法について
dodaチャレンジでは、登録が完了すると数日以内にキャリアアドバイザーから面談予約の案内が届きます。
この面談は、今後の転職活動の方針を一緒に考える大切なステップであり、あなたの強みや希望、職場に求める配慮についてじっくり話せる機会です。
面談はオンラインまたは電話で行われるため、全国どこからでも参加できますし、遠方に住んでいる方でも安心です。
予約方法はとてもシンプルで、メールやマイページ上で希望日程を伝えるだけ。
平日だけでなく土日対応してくれることもあるので、働きながらの転職活動でも無理なくスケジュールが組めます。
また、面談時の服装についても「スーツ不要」で、「ラフな私服でOK」というカジュアルなスタイルです。
実際の面談では1時間〜1時間半程度の時間をかけて丁寧にヒアリングしてくれますので、不安なことや聞きたいことがあれば遠慮せずに相談してみましょう。
「こんなこと話してもいいのかな?」と感じるような内容でも、しっかり受け止めてくれるのがdodaチャレンジのアドバイザーの魅力です。
| 【面談について】
オンライン or 電話面談(地方でもOK) |
dodaチャレンジの面談の内容について
dodaチャレンジの面談では、キャリアアドバイザーがあなたの状況をしっかり理解した上で、今後の転職活動を一緒に考えてくれます。
特に障がい者雇用に特化しているため、一般的な転職面談とは違い、「配慮してほしいこと」「働くうえでの不安」「希望する働き方」など、デリケートな内容にも寄り添ったヒアリングが行われます。
話す内容は事前に準備しておかなくても大丈夫ですが、「どんな職場なら働きやすいか」「どのような業務が得意か」「通勤や勤務時間に制限があるか」など、自分の気持ちを正直に伝えることが大切です。
担当者はあなたの話をもとに求人を選んでくれるため、ここでの会話が今後のマッチング精度を大きく左右します。
また、今までの職歴やスキル・資格についても簡単に聞かれるので、履歴書に書ききれないようなエピソードなどもぜひ共有してみてください。
過去の経験から自分では気づかなかった「強み」が見つかることもありますよ。
キャリアプランについても堅苦しく考える必要はなく、「こんな働き方ができたらいいな」という理想を気軽に話すところからスタートできます。
| 【面談の内容】
障がいの内容や、必要な配慮 |
dodaチャレンジの求人紹介の流れについて/キャリアアドバイザーがあなたに合う求人をピックアップしてくれる
dodaチャレンジでは、登録・面談後、キャリアアドバイザーがあなたの状況や希望条件をもとに、最適な求人をピックアップしてくれます。
職種、勤務地、勤務形態、配慮事項など、事前のヒアリングをふまえてマッチングされるため、「自分に合った仕事が見つからない」と感じていた方にも安心の仕組みです。
紹介される求人の多くは非公開求人で、大手企業や安定した企業の案件も豊富。
あなたのスキルや経験に合わせて「今の自分にぴったりの職場」を見つけやすくなっています。
また、「自分に何ができるかわからない」という方には、強みを引き出す提案型のサポートも行われているため、安心して相談できます。
dodaチャレンジの書類作成・応募・面接サポートの流れについて
転職活動で不安が多い「書類作成」や「面接対策」についても、dodaチャレンジでは一人で抱え込む必要はありません。
キャリアアドバイザーが丁寧にサポートしながら進めてくれるため、初めての転職でも安心して挑戦できます。
特に障がいに関する記載や配慮事項の伝え方など、通常の転職サービスでは得られないきめ細かな指導が受けられるのが大きな特徴です。
履歴書・職務経歴書を担当者が一緒に作ってくれる
書類作成に自信がない方でも安心してください。
dodaチャレンジでは、履歴書や職務経歴書の書き方を一から丁寧に教えてもらえます。
自分では気づかなかったスキルや経験を一緒に掘り起こし、読みやすく、かつ好印象を与える形で仕上げてもらえるため、「書類で落とされるかも…」という不安が減ります。
また、応募する企業ごとに内容を調整してくれるので、より効果的なアピールが可能になります。
完全オーダーメイドのサポートを受けられるのは、専門エージェントならではの強みです。
障がいに関する説明や配慮事項の伝え方まで、文章を添削してもらえる
履歴書や職務経歴書では、障がいについてどのように書くべきか迷う方も多いと思います。
dodaチャレンジでは、その点もプロのアドバイザーがしっかり添削し、正直さと前向きさのバランスをとった表現に仕上げてくれます。
「どこまで書けばいい?」「ネガティブに取られないかな?」という不安を解消できるため、安心して応募に踏み出せます。
文章に自信がない方や、伝え方に悩む方こそ、ぜひこのサポートを活用してください。
模擬面接を実施(オンライン or 電話)してくれる
面接が苦手な方には、模擬面接が特におすすめです。
オンラインまたは電話で実施される模擬面接では、実際の企業でよく聞かれる質問を想定して練習ができ、フィードバックも具体的でもらえます。
障がいについての説明や職場に求める配慮など、伝えるべき内容を練習しておくことで、自信を持って本番に臨めるようになります。
緊張しやすい方や、話し方に不安がある方にとっては、内定にグッと近づく重要なステップです。
企業とのやり取り(応募書類提出、面接日調整)は全部アドバイザーが代行してくれるから安心
応募書類の提出や面接日程の調整など、企業とのやり取りはすべてdodaチャレンジのアドバイザーが代行してくれます。
自分で直接やりとりをする必要がないため、スケジュール調整や連絡のプレッシャーから解放され、転職活動に集中できます。
さらに、企業への条件確認や配慮事項の共有もアドバイザーが行ってくれるので、「自分で伝えにくい内容がある」「交渉が苦手」という方でも安心です。
まさに“伴走型サポート”を受けながら、落ち着いて転職活動を進められる仕組みです。
dodaチャレンジの面接~内定までの流れ
dodaチャレンジでは、応募から内定までの一連の流れにおいて、キャリアアドバイザーが常に伴走してくれます。
書類提出や面接日程の調整といった事務的なことはもちろん、面接で伝えるべき内容や表現方法についても事前にアドバイスをもらえるため、安心して選考に臨むことができます。
また、面接後には企業側からのフィードバックも共有してもらえるため、自分の改善点や強みを客観的に把握できるのも大きなポイントです。
さらに、面接に同席してくれるケースもあるので、緊張しやすい方や伝え方に不安がある方にとっては大きな支えになります。
内定までの過程は決して一人ではなく、プロの支援と共に進められるので、転職活動そのものが心強く感じられるでしょう。
内定後も条件面(給与、勤務時間、配慮内容)をアドバイザーがしっかり交渉してくれる
無事に内定が出たあとも、まだ終わりではありません。
dodaチャレンジでは、入社前に確認すべき条件面――たとえば給与の詳細、勤務時間、出勤日数、休暇制度、そして障がいに関する配慮内容について、キャリアアドバイザーが企業としっかり交渉してくれます。
「自分で条件交渉をするのは難しい」「言いづらい」と感じる方でも、代わりにプロが伝えてくれるので、安心して自分の希望を実現できます。
特に配慮事項は、言葉選びひとつで伝わり方が大きく変わるため、プロの介入によってスムーズなコミュニケーションが期待できます。
曖昧なまま入社してしまうリスクを避け、納得感を持って新たなスタートが切れるようサポートしてくれます。
内定後も「自分に合わない」と思ったら、辞退しても問題ありません
dodaチャレンジでは、内定が出たからといって必ずしも受けなければならないということはありません。
条件をよく確認したうえで、「自分には合わないかもしれない」と感じた場合には、辞退してもまったく問題ありません。
アドバイザーもその判断を尊重してくれるので、プレッシャーなく判断できる環境が整っています。
むしろ、「なんとなく不安だけど受けるしかない…」と無理して入社するよりも、自分に合った職場を納得して選ぶことが大切だと考えられているため、複数の選択肢を見比べながら進めていくスタイルが推奨されています。
アドバイザーも「次にもっと合う企業を一緒に探しましょう」と前向きに提案してくれるので、安心して転職活動を継続できます。
dodaチャレンジの入社からその後のフォローの流れについて
dodaチャレンジの魅力の一つが、「入社したら終わり」ではないという点です。
多くの転職サービスでは、内定・入社がゴールになってしまうこともありますが、dodaチャレンジはむしろ“入社後”を非常に大切にしており、継続的なサポートが受けられます。
職場に慣れるまでの間、そしてその後も、定期的な面談や企業との橋渡しを通じて安心して働ける環境を整えてくれます。
実際に、「職場で困った時にすぐに相談できた」「人間関係の悩みをアドバイザーが聞いてくれて救われた」といった声も多く、心の支えとして機能している利用者も多いです。
ここでは、入社後のフォロー体制について詳しくご紹介します。
定期的に面談がある(1〜3ヶ月に1回が多い)
入社後は、1〜3ヶ月に1回程度のペースで、アドバイザーとの面談が行われます。
面談の頻度は人によって異なりますが、特に入社直後や環境に慣れるまでの間は、やや短めのスパンでのサポートが設定されることもあります。
この面談では、業務の状況や人間関係、職場で困っていることなど、あらゆる内容について自由に相談ができます。
話した内容は、希望すれば企業側にも共有してくれるため、「自分からは言い出しづらいけど、なんとかしたい」という悩みを解決するきっかけにもなります。
「職場に言いにくいこと」をアドバイザーが企業に伝えてくれる
職場で働いていると、「こんなこと言ってもいいのかな?」と感じてしまうことってありますよね。
たとえば、仕事量が多いと感じた時や、同僚との関係で悩んでいる時、環境のちょっとした変化に戸惑っている時など。
そんな時も、dodaチャレンジのアドバイザーに相談すれば、必要に応じて企業側にやんわりと伝えてくれます。
自分で直接言いにくいことを第三者が代弁してくれることで、職場でのストレスがぐっと軽減されますし、無理をしすぎずに働き続けられる環境づくりに役立ちます。
特に精神的な負担がかかりやすい方にとっては、この仕組みがあるだけで安心感がまるで違います。
人間関係や仕事内容で悩んだ時も、すぐ相談できる
dodaチャレンジのアフターフォローは、困った時にすぐ相談できる“身近な相談相手”として機能してくれます。
職場の人間関係や仕事内容について、「なんとなく合わないかも」「この作業がどうしても苦手」など、日々のモヤモヤを誰かに聞いてもらえるだけで、気持ちが楽になることもありますよね。
相談は電話やオンラインで行えるので、忙しい方や通院などで時間に制約がある方でも無理なく利用できます。
また、必要に応じてアドバイザーが企業と調整を行ってくれるので、状況が大きく悪化する前に改善へとつなげることができます。
「一人で抱え込まなくていい」安心感が、長く働くための大きな支えとなってくれます。
dodaチャレンジの登録に必要なものを紹介します/面談までに準備しておくとスムーズです
dodaチャレンジをスムーズに利用するためには、登録時や初回面談までに最低限そろえておきたい準備があります。
といっても、すべてを完璧に用意する必要はありません。
「まだ履歴書が書けていない」「障がい者手帳が手元にない」といった場合でも、登録や相談は問題なく行えますので安心してください。
ただし、あらかじめいくつかの基本情報を用意しておくことで、キャリアアドバイザーとの面談がより具体的で有意義な時間になります。
特に履歴書や職務経歴書が手元にあれば、職務の棚卸しがスムーズになり、マッチする求人の精度も高まります。
また、メールアドレスや電話番号は今後の連絡手段として必須なので、すぐ確認できるものを登録するようにしましょう。
以下の表に、登録時に必要となる代表的な項目と、その内容をまとめました。
面談日までに無理のない範囲で準備しておくと、より安心してdodaチャレンジのサービスを活用できます。
| 必要なもの | 詳細 |
| メールアドレス | 登録&連絡用(PC・スマホどちらでもOK) |
| 電話番号 | 連絡用。オンライン面談でも使うことがある |
| 障がい者手帳(任意) | 持っていれば◎(無くても登録・相談はできる) |
| 履歴書・職務経歴書(任意) | 面談までに準備しておくとよい |
dodaチャレンジの口コミは?dodaチャレンジの解約方法や解約前の注意点について解説します
dodaチャレンジを利用している中で、「少し休みたい」「一時的に転職活動をストップしたい」と思うこともあるかもしれません。
そのような場合、すぐにアカウントを削除してしまうのはちょっと待った方がいいかもしれません。
というのも、アカウントを削除することで、サポートが完全に終了し、再利用時にも一からやり直しになってしまうためです。
この記事では、dodaチャレンジの解約(退会)方法と、解約前に知っておくべき注意点を詳しく解説します。
勢いで削除して後悔しないためにも、事前にポイントを押さえておくと安心です。
解約前の注意点1・アカウント削除するとサポートが完全に終了する
dodaチャレンジを退会すると、これまで受けていたサポートや連絡の履歴、求人情報などがすべて利用できなくなります。
転職活動を一時的にストップしたいだけのつもりでアカウントを削除してしまうと、再開時に改めて登録し直す必要があり、過去の履歴も引き継がれないため不便になるケースも多いです。
特に、すでに面接日程の調整を進めていたり、書類選考が進行中の状態でアカウントを削除してしまうと、それらの選考が自動的にキャンセルされてしまう恐れもあるため要注意です。
焦って判断するのではなく、まずは担当アドバイザーに相談して、他の選択肢がないかを確認するのがおすすめです。
| 【アカウント削除するとできなくなること】
・紹介されていた求人情報が見れなくなる |
担当者に「一時的に休みたい」と相談しておけば、退会しなくてもサポートを一時停止してくれることがある
「転職活動の優先度を下げたい」「少し気持ちが疲れてしまった」といった理由で利用を一時停止したい場合は、いきなり退会する必要はありません。
dodaチャレンジでは、担当アドバイザーに「一時的にお休みしたい」と伝えれば、状況に応じてアカウントを維持したままサポートを一時停止することも可能です。
この方法であれば、登録情報や過去のやりとりはそのまま残り、再開したい時にスムーズにサポートを受けられるので非常に便利です。
無理に退会せず、まずは「相談ベース」で止める形をとることで、再出発もしやすくなります。
迷ったときは、ぜひ気軽に担当者へ連絡してみてくださいね。
解約前の注意点2・応募中の企業があればキャンセル連絡を忘れずにしましょう
dodaチャレンジを解約する前に、最も大切なことのひとつが「応募中の企業への対応」です。
すでに書類選考や面接が進行中の企業がある場合は、必ずその応募を辞退する旨を、キャリアアドバイザーまたは企業側に明確に伝えておく必要があります。
これを怠ると、企業に迷惑がかかるだけでなく、dodaチャレンジ側の信頼も損なってしまう恐れがあります。
また、面接日が確定していたり、内定の連絡待ちだった場合など、途中で連絡が取れなくなると、「連絡なしの辞退」として扱われる可能性があり、次回以降の活動にも影響が出てしまうことがあります。
解約や利用終了を考えているタイミングでは、「自分だけの判断」で進めるのではなく、必ずアドバイザーに相談し、必要なキャンセル手続きを適切に行うようにしましょう。
応募中の企業はすべて辞退すると明確に伝えておく
応募中の企業がある場合、「すべて辞退したい」という意思をしっかりと伝えることが大切です。
中途半端にしておくと、企業側が「まだ選考を進めるつもりなのか」と誤解し、無駄に待たせてしまう結果になりかねません。
キャリアアドバイザーにまとめて伝えれば、本人に代わって企業へ辞退連絡をしてくれるため、心理的な負担も少なく済みます。
特に、複数の企業に応募していた場合は、自分で管理しきれないケースも多いため、「すべて辞退したいです」と一言添えておくのがベストです。
誠意ある対応が、将来また転職活動を再開する際にもプラスに働いてくれます。
辞退理由は無理に詳しく説明しなくても大丈夫
辞退の際に「なぜやめるのか」「どんな理由があるのか」と聞かれることを不安に感じる方もいるかもしれませんが、心配はいりません。
dodaチャレンジでは、辞退理由について無理に詳しく伝える必要はありませんし、「一身上の都合」や「事情により一旦活動を中止したい」などの簡単な説明で十分です。
キャリアアドバイザーも、こうしたケースには慣れているため、深く詮索するようなことはありませんし、丁寧に対応してくれます。
逆に無理に理由を作ろうとすると精神的に負担がかかってしまうので、自分の気持ちを優先して「無理のない形」で辞退することが、長い目で見ても良い判断につながります。
解約前の注意点3・内定後のアフターフォローが受けられなくなります
dodaチャレンジの大きな魅力のひとつが、「内定をもらった後も続くサポート」です。
入社前の条件確認や、入社後の定着支援など、他の転職サービスでは得られない手厚いフォロー体制が整っています。
しかし、もし内定後すぐにアカウントを削除してしまうと、これらのアフターサポートを受けることができなくなります。
たとえば、入社直前になって不安や変更事項が出てきたとき、サポートがないと自力で対応しなければならず、不安やストレスが増してしまうこともあります。
特に障がいのある方の場合、ちょっとした変化が大きな負担になるケースもあるので、安定して働き始めるまではアカウントを維持しておくのがおすすめです。
入社までは解約せずに入社して環境が安定してから退会するのがおすすめ
アカウントの削除は、必ずしも急ぐ必要はありません。
むしろ、入社して環境に慣れ、安心して働ける状態になってから「もう大丈夫」と判断できたタイミングで退会を検討するのがベストです。
dodaチャレンジのアドバイザーは、入社後の悩みや課題についても相談に乗ってくれるので、最初の数ヶ月は特に心強い存在になります。
焦って退会してしまうと、いざというときに相談先がなくなってしまうことも。
せっかくの支援を受けられなくなるのはもったいないので、少し余裕を持ったタイミングで判断するようにしましょう。
解約前の注意点4・アカウント情報は完全に削除され復元はできない
dodaチャレンジを退会・解約すると、登録していたアカウント情報はすべて削除され、復元することはできません。
つまり、一度退会してしまうと、履歴書や職務経歴書、希望条件や配慮事項のメモ、アドバイザーとのやりとりの記録などもすべて失われてしまいます。
再度登録する場合も、最初からすべて入力し直す必要があり、非常に手間がかかります。
このような事態を避けるためにも、「また利用する可能性が少しでもある」という方は、すぐに退会せず、まずは“休止”という形を選ぶのが賢明です。
キャリアの記録を残す意味でも、完全削除は最終手段と考えるようにしましょう。
| 【削除される情報】
・ 履歴書・職務経歴書 |
また利用する可能性がある人は退会ではなく休止扱いで残すのがおすすめ
「今は転職活動をやめたいけれど、いずれまた再開するかもしれない」と感じている方は、退会ではなく“利用休止”という選択肢がとても便利です。
休止であれば、登録情報や書類、アドバイザーとのやりとりが保持されたままになるため、再開時にゼロからのスタートにならず、すぐに活動を再開できます。
また、休止中も連絡は控えめにしてもらうよう調整できるため、「少し距離を置きたいけど繋がりは残したい」という方にもぴったりです。
データ消去前に、自分で書類や情報を保存しておくとよい
どうしても退会する必要がある場合は、消去される前に自分で必要なデータを保存しておくのがポイントです。
特に、アドバイザーと一緒に作成・添削した履歴書や職務経歴書は、自分で転職活動を再開する際にも役立ちます。
PDFやWord形式で保存しておけば、他のサービスを利用する場合にもスムーズに再利用できますし、過去の応募記録や企業とのやりとりも参考資料として活かせます。
せっかくの努力と記録を無駄にしないためにも、保存は忘れずに行っておきましょう。
解約前の注意点5・他のサービスとの併用も検討してから決めましょう
dodaチャレンジを解約しようと考えるタイミングでは、「他のサービスの方が合っているかもしれない」「思ったよりサポートが合わなかった」と感じることもあるかもしれません。
でも、だからといってすぐに完全退会してしまうのは、ちょっともったいないこともあるんです。
なぜなら、転職支援サービスは一つに絞る必要はなく、併用して比較しながら進めることができるからです。
特に、LITALICOワークス、ミラトレ、atGPエージェントなど他の就労支援サービスと併用しながら、自分に合うアドバイザーや求人の傾向を見極めていくのが賢いやり方。
複数の視点からアドバイスを受けることで、自分の強みや希望条件の再確認にもつながります。
dodaチャレンジは非公開求人や条件交渉の強さに定評がありますが、他のサービスにはまた別の良さがあるものです。
「何か違うかも?」と感じたときは、一度立ち止まり、まずは他のサービスも使ってみてから判断することで、自分にとってベストな環境が見えてくることもあります。
複数サービスを併用して自分に合うところだけ継続利用するのがおすすめ
転職活動は“情報戦”でもあるので、複数のサービスを併用して、求人の質・対応の仕方・相性の良さを比較していくのは非常におすすめです。
dodaチャレンジのように非公開求人に強いサービスもあれば、LITALICOワークスのように対面サポートに特化したところもありますし、ミラトレのように実習を重視するところもあります。
複数を使っていく中で、「この人のサポートは安心できる」「ここの求人は自分に合っている」といった実感が持てるようになってきます。
そこから最終的に1〜2社に絞っていけばOK。
最初から「どこか一つに絞らないといけない」と思い込まず、まずは気軽に試してみるくらいの気持ちでスタートするのが、転職成功への近道です。
dodaチャレンジの解約(退会)の流れを解説します
「dodaチャレンジを退会したいけれど、どうすればいいかわからない」「退会って面倒なのでは?」と不安に感じている方もいるかもしれません。
でもご安心ください。
dodaチャレンジの解約(退会)手続きはシンプルで、担当キャリアアドバイザーに伝えるだけで進められます。
ただし、退会にあたってはいくつかのステップがあります。
急ぎの退会でなければ、できるだけ丁寧に対応することで、再利用時にもスムーズに関係を再構築できるようになります。
ここでは、具体的な退会の流れを3つのステップに分けて解説します。
解約の流れ1・担当キャリアアドバイザーに退会希望を伝える
まず、退会したいと思ったら最初にすべきことは、担当のキャリアアドバイザーへ「退会したいです」と伝えることです。
メールや電話、またはマイページの問い合わせフォームから連絡することができます。
気を遣う必要はなく、正直に「転職活動を一度やめたい」「他のサービスを利用したい」といった理由でOKです。
ここで大切なのは、「連絡をしないままフェードアウトしない」こと。
アドバイザーはあなたのために動いてくれている存在なので、一言でも伝えておくことで、お互いに気持ちよく区切りをつけることができます。
解約の流れ2・退会の理由などの確認をするためヒアリングを受ける
退会の意思を伝えると、アドバイザーから「差し支えなければ退会理由を教えてください」といったヒアリングがあります。
これは、今後のサービス改善やアドバイザーの対応向上のために行われるもので、無理に詳しく説明する必要はありません。
「環境が整ったから」「転職活動を休止したい」など、簡単な理由で構いません。
また、アドバイザーによっては「休止扱いもできますよ」といった提案をしてくれることもあります。
完全に退会するか、一時的に活動をストップするか迷っている方は、このタイミングで相談してみるのもおすすめです。
解約の流れ3・個人情報を削除し退会となる
退会の意向が確認されると、登録していた情報(履歴書・職務経歴書・希望条件・やりとりの履歴など)がすべて削除されます。
これにより、dodaチャレンジのアカウントは完全に閉鎖され、サービスの利用はできなくなります。
一度削除された情報は復元できないため、必要なデータは事前にダウンロードやコピーをしておくことを強くおすすめします。
また、退会後に再登録することは可能ですが、すべての情報を再入力し直す必要がありますので、時間と手間がかかる点も考慮して判断しましょう。
dodaチャレンジの口コミや評判はやばい!?怪しいなど悪い噂の理由について検証しました
インターネット上で「dodaチャレンジは怪しいのでは?」「やばいって本当?」といった声を見かけることがありますが、結論から言えば、それは誤解や情報不足によるものであるケースがほとんどです。
特に障がい者専門の転職支援サービスという特性上、一般の転職サービスとは異なるアプローチをとっているため、「なんとなく怪しく見える」と感じてしまう方もいるようです。
しかし、dodaチャレンジは大手パーソルグループが運営する正規のサービスで、法的にも業界的にも信頼性の高い実績があります。
ここでは、なぜこのような“誤解”が生まれるのか、その背景と実際の状況について丁寧に紐解いていきます。
理由1・障がい者専門の転職エージェントという特殊性が怪しく感じる人がいる
dodaチャレンジは「障がい者の就職・転職支援」に特化した専門エージェントという点で、一般的な転職サイトとは一線を画しています。
そのため、「聞いたことがない」「普通の転職エージェントと違う」という理由だけで、少し警戒心を持たれてしまうことがあるのも事実です。
とくにネット検索で“やばい”などのワードがヒットすると、不安になってしまうのは無理もありません。
ただし、この“特殊性”こそがdodaチャレンジの最大の強みでもあります。
障がいのある方が安心して働ける職場を見つけるために、専門知識をもったアドバイザーがサポートしてくれるのは、むしろ非常に心強い存在なのです。
障がい者雇用促進法やSDGsの流れで、障がい者雇用枠を設ける企業は年々増加中
実際、企業が障がい者雇用に積極的になる背景には、法制度の整備や社会的意識の変化があります。
たとえば「障がい者雇用促進法」では、企業に対して一定の割合で障がい者を雇用する義務があり、これを満たさないと納付金が発生する仕組みになっています。
さらに最近では、SDGs(持続可能な開発目標)の観点からも、多様性を受け入れる企業文化が求められており、障がい者雇用に力を入れる企業が年々増えています。
そうした流れの中で、dodaチャレンジのような専門サービスのニーズは着実に高まっており、「怪しい」どころか、社会的にも意義ある取り組みとして評価されています。
障がい者雇用は需要と供給のバランスが合っている
障がい者雇用の現場では、「雇いたい企業」と「働きたい人材」の双方のニーズが非常に明確です。
企業は、障がいへの理解と配慮が前提となった求人を出しており、働く側も自分に合った条件での就職を望んでいるため、マッチングの成功率が高い傾向にあります。
dodaチャレンジは、こうした“供給と需要のバランス”を上手く取り持つ役割を果たしており、「紹介される求人がリアルで、自分に合っていた」という口コミが多いのも特徴です。
つまり、利用者と企業双方にとってメリットの大きいサービスであることが、怪しいどころか“合理的”で“実践的”な選択肢である証でもあります。
理由2・登録後に連絡が頻繁に来た・しつこい電話やメールがあるとの口コミが一部ある
dodaチャレンジに対して「登録後に電話やメールが多かった」「連絡がしつこいと感じた」という口コミを目にすることがあります。
このような声は実際に少数存在しますが、これには理由があります。
dodaチャレンジは一人ひとりに専任のキャリアアドバイザーがつき、応募や面接のスケジュール調整、企業との連絡、配慮事項の確認など、細やかなサポートを提供するのが特徴です。
連絡の頻度が多く感じるのは、それだけ密にサポートを行っている証拠でもあります。
もちろん、人によって「もう少しゆっくり進めたい」と思うこともあるかと思いますが、その場合は「連絡は週に1回で大丈夫です」などと要望を伝えることで、対応を調整してもらうことが可能です。
連絡の多さは「やる気の押し売り」ではなく、「あなたのために動いている」サインでもあるのです。
内定をサポートするために小まめに連絡をすることもあります
dodaチャレンジのアドバイザーが頻繁に連絡をくれるのは、あなたがより良い職場に就けるよう全力でサポートしているからです。
求人情報の更新、書類の添削タイミング、面接の日程変更、企業側の要望など、タイムリーに動かなければならないことが多いため、連絡の回数が多くなる傾向があります。
この連絡をうまく活かせば、選考の通過率が高まったり、内定後の条件交渉もスムーズに進められる可能性が高まります。
無理に急かすような連絡があればその旨を伝えて構いませんが、「きめ細かく連絡をくれる」という視点で受け止めると、dodaチャレンジの価値がより実感できるはずです。
理由3・成果報酬型(企業から報酬をもらう)のビジネスモデルへの不信感を持つ人がいる
一部の人の中には、「dodaチャレンジって、企業から報酬をもらってるんでしょ?だったら利用者より企業の都合を優先するんじゃないの?」といった不信感を抱く方もいるかもしれません。
確かに、dodaチャレンジは成果報酬型のビジネスモデルを採用しており、求職者が企業に入社したタイミングで企業側から報酬を受け取る仕組みです。
しかし、これはdodaチャレンジに限らず、リクナビやマイナビなど、ほぼすべての転職エージェントが採用している一般的なモデルです。
求職者からは一切料金を取らず、無料で質の高いサポートが受けられるのは、この仕組みがあるからこそ。
企業に対しても、入社後すぐに辞められては意味がないため、dodaチャレンジ側も「長く働ける人材の紹介」に本気で取り組んでいます。
成果報酬型は、ほとんどの転職エージェントで採用されているビジネスモデル
転職エージェント業界では「成果報酬型」はスタンダードな仕組みであり、dodaチャレンジだけが特別なわけではありません。
求職者から利用料を取らず、質の高い支援を提供できるのは、このモデルがあるからこそ成り立っています。
つまり、金銭的な負担なく、プロによるサポートを受けながら転職活動ができるという意味では、むしろ非常に合理的なサービスだと言えます。
また、成果報酬が発生するのは「実際に入社した場合のみ」なので、無理な勧誘や押し付けが起きにくい構造にもなっています。
dodaチャレンジの定着率は90%以上で長く働けるマッチングを最優先にしている
実際に、dodaチャレンジの職場定着率は90%以上と非常に高水準です。
これは、単に就職をゴールにするのではなく、「長く働ける職場に出会う」ことを最優先にサポートしている証です。
アドバイザーがしっかりとヒアリングを行い、本人の希望や特性、職場での配慮事項まで把握したうえで、ミスマッチの少ない求人を提案しているからこその実績です。
成果報酬型であっても、単なる“紹介して終わり”ではなく、その後の定着や満足度を重視しているため、安心して利用することができます。
理由4・求人が偏っている、求人数に限界があると感じる人がいる
dodaチャレンジを利用した方の中には、「紹介される求人のジャンルが偏っている気がする」「自分が希望する職種がなかなか見つからなかった」という声をあげる人もいます。
確かに、障がい者雇用枠に限定された求人は、一般枠と比較するとまだまだ数も種類も限られているのが実情です。
これはdodaチャレンジに限らず、業界全体の課題とも言える点です。
特に事務系・軽作業系・コールセンターなど、比較的導入しやすい業務に求人が集中しやすく、「もっと専門的な仕事がしたい」「キャリアアップを目指したい」と考えている方には物足りなさを感じることがあるのも事実です。
しかし一方で、dodaチャレンジは大手・優良企業の非公開求人を多く扱っており、探せば意外な選択肢が見つかることもあるため、粘り強くアドバイザーに相談するのが大切です。
障がい者雇用枠は企業の数や職種がまだ限られているのが現実
障がい者雇用枠での採用は、法制度の後押しもあり年々拡大していますが、それでも企業側が対応可能な職種には限りがあるのが現実です。
たとえば「配慮しやすい環境を整えやすい職種」や「業務内容を明確に区切れる職場」に求人が集中しがちです。
そのため、ある程度の偏りが出るのは避けられません。
ただし、これは今後の社会的な意識改革や制度の見直しによって少しずつ改善されていく分野でもあります。
今はまだ選択肢が狭く感じられるかもしれませんが、その中でも「働きやすさ」や「自分のスキルを活かせる場所」を丁寧に探すことで、希望に近い働き方が実現することも少なくありません。
「クリエイティブ職」「管理職」「未経験のエンジニア」など、人気や専門性が高い職種は競争が激しい
特に注意が必要なのが、デザイナーや動画編集といった「クリエイティブ職」、マネージャーポジションにあたる「管理職」、そして未経験者を歓迎する「ITエンジニア」など、人気がありつつ専門性も高い職種を希望する場合です。
これらの求人は求職者の希望が集中するため、応募の競争率が非常に高くなります。
dodaチャレンジでもこのような求人は扱っているものの、募集数自体が少ないため「希望したけれど紹介されなかった」というケースが出てしまうのも理解できます。
そのような場合は、アドバイザーと相談しながら「関連職種」や「今後のステップアップに繋がる求人」を視野に入れて探していくことが、長期的なキャリア形成には効果的です。
理由5・内定がもらえないと不満を持つ人がいる
dodaチャレンジを利用していても、「なかなか内定がもらえない」「サポートは丁寧だけど結果が出ない」と感じてしまう方も一定数いらっしゃいます。
とくに就職活動に不安を抱えている方にとって、期待して登録した分、結果がすぐに出ないと「自分には合わなかったのかも」「サポートが足りないのでは」と不満を持ってしまうこともあるかもしれません。
しかし、内定の有無はあくまで企業側との相性やタイミング、そしてその人の希望条件とのマッチ度によって左右される部分が大きく、dodaチャレンジ側がどれだけ手厚くサポートしても、100%結果を保証することはできません。
大切なのは、アドバイザーと一緒に自分の希望条件や方向性を見直したり、面接や書類の改善点を少しずつブラッシュアップしていく姿勢です。
dodaチャレンジはサポートは手厚いが内定が保証されるわけではない
dodaチャレンジの魅力は、履歴書・職務経歴書の添削、模擬面接、配慮事項の整理、企業とのやりとり代行など、多角的にサポートしてくれる点にあります。
しかし、これはあくまで「内定を勝ち取るためのサポート」であり、「内定を確実に出してくれる」わけではありません。
転職市場は日々変化しており、同じ求人でもライバルの応募状況や企業の採用基準の微調整によって、合否が大きく分かれることも珍しくありません。
そのため、結果に一喜一憂しすぎず、「どうすれば次は通過できるか」「もっと自分に合う企業はどこか」と考える姿勢がとても大切です。
また、希望条件が厳しすぎたり、自分の強みがうまく伝えられていない可能性もあるため、アドバイザーと一緒に視点を変えてみることで、思いがけないチャンスに出会えることもあります。
焦らず、一歩ずつ進めていきましょう。
dodaチャレンジの口コミは?dodaチャレンジの会社概要について紹介します
dodaチャレンジを利用するうえで、「この会社ってどんなところが運営しているの?」「信頼できる会社なのかな?」と気になる方も多いと思います。
サービスの質はもちろん大事ですが、運営元の企業について理解しておくことも、安心して利用するうえで欠かせないポイントです。
dodaチャレンジを運営しているのは「パーソルダイバース株式会社」。
名前のとおり、パーソルグループに属する企業で、障害者雇用に関わるさまざまな支援やコンサルティング、就労移行支援事業を行っています。
実績も多く、全国的に幅広いサービスを展開している信頼性の高い企業です。
ここでは、会社の所在地や設立情報、事業内容などの基本情報を一覧にまとめましたので、参考にしてみてくださいね。
| 社名 | パーソルダイバース株式会社 |
| 所在地 | 〒108-0075 東京都港区港南1-7-18 A-PLACE品川東 6F |
| 電話番号 | 03-6385-6143 |
| 設立 | 2008年1月1日(特例認定 2008年11月) |
| 従業員 | 2,783名 |
| 役員 | 代表取締役社長 渡部 広和 |
| 事業内容 | 障害者雇用に関わる有料職業紹介事業・コンサルティング事業、就労移行支援事業、 事務アウトソーシング、食品の製造および販売、農業及び農産物の販売、 繭・生糸及び絹糸の加工並びにその製品・加工品の開発及び販売 |
参照:会社概要(パーソル ダイバース株式会社)
dodaチャレンジの口コミはどう?についてよくある質問
dodaチャレンジを検討している方にとって、「実際に使っている人はどう感じているの?」「利用者のリアルな声が知りたい」と思うのは自然なことです。
口コミや評判は、公式サイトの説明やサービス紹介よりも、実際の利用体験を通じた“本音”が詰まっているため、判断材料として非常に参考になります。
ここでは、dodaチャレンジについて寄せられているよくある質問や口コミにまつわる疑問を、Q&A形式でわかりやすく解説していきます。
dodaチャレンジの口コミや評判について教えてください
dodaチャレンジの口コミには、「丁寧な対応で安心できた」「自分に合った求人を紹介してもらえた」「障がいへの配慮をしっかり考えてくれる」といったポジティブな声が多く見られます。
特に、キャリアアドバイザーが親身にヒアリングしてくれること、書類添削や模擬面接などのサポートが充実している点が高く評価されています。
一方で、「希望職種が少なかった」「連絡が多くて疲れた」という声も一部にありますが、これらは人によって感じ方が分かれる部分でもあります。
連絡頻度などはアドバイザーに相談すれば調整できるため、過剰に不安になる必要はありません。
全体としては、「安心して任せられる」「自分らしく働ける職場を一緒に探してくれた」という満足度の高い意見が多く、障がい者雇用に特化した転職サービスとして、信頼性の高い選択肢のひとつといえるでしょう。
関連ページ:dodaチャレンジの口コミはどう?障害者雇用の特徴やメリット・デメリットをやさしく解説
dodaチャレンジの求人で断られてしまったらどうすれば良いですか?
dodaチャレンジを利用していて応募した企業から不採用の通知が届いたとき、落ち込んでしまうのは当然のことです。
でも、それで「自分には向いていない」と決めつけてしまうのは早すぎます。
転職活動では複数回の不採用があるのは当たり前。
むしろ、その経験を次に活かしていくことがとても大切です。
まずは、アドバイザーに不採用理由を確認してみましょう。
企業から直接的なフィードバックが来ることは少ないですが、傾向や評価のポイントをアドバイザーが把握していれば、それをもとに履歴書や職務経歴書、面接での受け答えを改善することができます。
また、応募企業とのミスマッチがあった場合も、アドバイザーがよりマッチする求人を新たに提案してくれる可能性があります。
落ち込む気持ちを一度受け止めた上で、「なにがダメだったか」ではなく、「どうすれば次に進めるか」という視点に切り替えることがポイントです。
自分一人で抱え込まず、dodaチャレンジのプロと一緒に次の一歩を踏み出しましょう。
ひとつの不採用が、より自分に合った職場との出会いへのきっかけになることもあります。
関連ページ:dodaチャレンジで断られた!?断られた理由と対処法/難しいと感じた体験談
dodaチャレンジで面談後に連絡なしの理由について教えてください
dodaチャレンジで面談を受けたあと、「その後連絡が来ない…」「放置されてるのかな?」と不安になることがありますよね。
でも、実際には“意図的に放置している”というより、いくつかの理由が重なって連絡が遅れてしまっているケースが多いです。
まず考えられるのは、アドバイザー側で求人情報の整理やマッチング調整に時間がかかっているという点です。
複数の企業と連携を取りながら、求職者一人ひとりに合う求人を提案するには、どうしても一定の準備期間が必要になります。
また、メールや電話での連絡ミスや、迷惑メールフォルダに振り分けられてしまうといった“すれ違い”も意外と多いです。
「待っているのに来ないな」と感じたら、一度こちらから確認の連絡を入れてみるとスムーズに進むことがよくあります。
アドバイザーも人間ですので、繁忙期には返信が遅れることもありますが、基本的には丁寧に対応してくれるはずです。
「連絡がない=見放された」と決めつけず、少しだけ勇気を出して問い合わせてみましょう。
その一歩が、新たな展開につながるかもしれません。
関連ページ:dodaチャレンジから連絡なしの理由と対処法/面談・求人・内定それぞれのケースと連絡なしの理由
dodaチャレンジの面談の流れや聞かれることなどについて教えてください
dodaチャレンジの面談は、転職活動をスムーズに進めるための最初の大切なステップです。
いきなり面接が始まるわけではなく、キャリアアドバイザーとの“対話”が中心になります。
堅苦しい雰囲気ではなく、リラックスした空気感の中で、これまでの職歴や希望条件、障がいの特性や配慮事項などを一緒に整理していく形で進んでいきます。
面談の流れとしては、まず基本的な自己紹介からスタートし、「現在の就業状況」「転職を考えるようになった背景」「どんな働き方を望んでいるか」などを順番にヒアリングされます。
また、障がいについても無理のない範囲で伝えるようにして大丈夫です。
「どんな配慮があると働きやすいか」など、実際の就業環境をイメージしながらアドバイザーが丁寧に聞き取ってくれます。
他にも「得意なこと・苦手なこと」「どんな職種を希望しているか」「1日の生活リズム」など、生活と仕事のバランスを考慮した質問も多く、あくまで“あなたらしい働き方”を一緒に見つけるための面談です。
話しづらいことがあれば無理に答える必要はありませんし、ゆっくり考えながら答えてOKです。
面談後には、希望条件に合う求人があるかどうかを探してもらい、後日あらためて連絡が来る流れになります。
初回面談が終わっただけで焦る必要はなく、自分のペースで進められるので安心してくださいね。
関連ページ:dodaチャレンジの面談から内定までの流れは?面談までの準備や注意点・対策について
dodaチャレンジとはどのようなサービスですか?特徴について詳しく教えてください
dodaチャレンジは、障がいのある方の就職・転職を専門にサポートする転職エージェントサービスです。
運営元は大手のパーソルグループで、全国規模で求人紹介や就職支援を展開しています。
一般的な転職サービスとの違いは、単に求人を紹介するだけでなく、「障がい特性に配慮した職場選び」や「就職後の定着支援」にも力を入れている点にあります。
キャリアアドバイザーは、障がいに関する専門知識を持っており、配慮事項の整理や職場への伝え方など、きめ細やかなサポートを受けられるのが特徴です。
書類添削や模擬面接、企業との条件調整も行ってくれるため、転職が初めての方でも安心して進められます。
また、大手・優良企業の非公開求人も多数保有しており、自分のスキルや希望条件にマッチした求人に出会いやすい環境が整っています。
障がい者手帳を持っていないのですが、dodaチャレンジのサービスは利用できますか?
障がい者手帳を持っていない方でも、dodaチャレンジのサービスに相談することは可能です。
必須ではないものの、実際に求人応募や障がい者雇用枠での選考に進む場合は、手帳の有無が条件となるケースが多いため、登録時にその旨を伝えておくのがベストです。
ただし、「まだ手帳を取得していないが、医師の診断を受けている」「取得を検討している」などの事情がある場合も、キャリアアドバイザーが個別に相談に乗ってくれます。
無理に準備を整える必要はなく、まずは今の状況を正直に伝えることで、自分に合った進め方を提案してもらえるでしょう。
dodaチャレンジに登録できない障害はありますか?
dodaチャレンジでは、身体障害・精神障害・発達障害・知的障害など、さまざまな障がいに対応していますが、「登録できない障害」が明確に決まっているわけではありません。
大切なのは、「就労に向けた意欲があるかどうか」と「就職を目指す上でどのような配慮が必要か」をアドバイザーと共有できることです。
一部の障がいや症状については、対応できる求人の数が限られている場合もあるため、まずは相談ベースで現状を伝えることが大切です。
dodaチャレンジでは、丁寧なヒアリングを通して一人ひとりに合ったサポート方法を一緒に考えてくれるので、不安がある方も安心して利用をスタートできます。
dodaチャレンジの退会(登録解除)方法について教えてください
dodaチャレンジを退会(登録解除)したい場合は、専任のキャリアアドバイザーに連絡すればスムーズに手続きが進みます。
メールや電話で「退会したい」と伝えるだけでOKで、複雑な手続きやフォームの入力は不要です。
退会前には、簡単なヒアリング(退会理由や今後の方針など)があることもありますが、無理に詳しく話す必要はありません。
また、「完全に辞めるのではなく一時的に休止したい」と伝えることで、アカウントやデータを残したままサポートを中断する選択肢もあります。
ただし、正式に退会すると、これまでの書類ややり取り履歴、希望条件の情報などが削除され、復元できなくなります。
再利用の可能性がある方は、データ保存をしてから退会することをおすすめします。
dodaチャレンジのキャリアカウンセリングはどこで受けられますか?
dodaチャレンジのキャリアカウンセリングは、全国どこにいても受けられるよう、主にオンライン(Zoomなど)や電話で実施されています。
自宅にいながらリラックスして受けられるのが大きな魅力で、移動が難しい方や地方在住の方にも配慮された体制になっています。
対応時間も柔軟で、平日の日中はもちろん、アドバイザーによっては夕方以降の相談に応じてくれることもあります。
また、首都圏など一部のエリアでは、オフィスに来社して対面での面談を行うことも可能です。
ただし、事前予約が必要で、空き状況によっては日程の調整が必要になることもあるため、オンライン面談が主流となっています。
どの方法でも、キャリアアドバイザーは丁寧に対応してくれるので、安心して相談できますよ。
dodaチャレンジの登録には年齢制限がありますか?
dodaチャレンジの公式には明確な年齢制限は設けられていませんが、実際には「就労意欲のある18歳以上の方」で、かつ「障がい者雇用枠での就職を希望している方」が主な対象となります。
20代〜40代の登録者が多い傾向にありますが、年齢よりも「就職活動の目的」や「働く意志」が重視されます。
50代以上の方や、ブランクのある方でも登録できるケースはあり、実際にサポートを受けて就職された実績もあります。
ただし、希望職種や地域によって求人の数が限られることもあるため、まずは一度相談してみるのがおすすめです。
アドバイザーが個別に可能性を探ってくれるので、年齢だけで諦める必要はまったくありません。
離職中ですがdodaチャレンジのサービスを利用できますか?
はい、dodaチャレンジは離職中の方でも問題なく利用できます。
むしろ、「いままさに仕事を探している」という方にとって、dodaチャレンジのサポートは非常に心強い存在になります。
離職中だからこそ、面談の時間を確保しやすく、書類の準備や面接練習などにもじっくり取り組むことができるメリットがあります。
また、離職の理由が精神的な事情や体調不良だった場合も、アドバイザーにしっかり伝えることで、無理のないペースで再スタートできるよう支援してくれます。
「ブランクがあるから不利かも…」と心配する必要はありません。
あなたの状況に合わせて、配慮ある求人を提案してくれるので、まずは気軽に相談してみましょう。
学生ですがdodaチャレンジのサービスを利用できますか?
原則として、dodaチャレンジは「就労を希望する社会人向け」の転職支援サービスです。
そのため、現役の学生(大学・専門学校等)で就職活動前の段階の方は、基本的には対象外となっています。
ただし、障がい者手帳を持っていて、卒業が近づいており「具体的に就職を考えている」という場合は、例外的に相談を受け付けてくれることもあります。
また、「在学中に転職を考えている社会人学生」や「通信制で働きながら学んでいる方」などは、ケースバイケースで対応されることがあります。
気になる場合は、まずは問い合わせフォームから現状を伝えたうえで、相談可能か確認してみるのが確実です。
就職に向けた情報収集の一環として活用するのも良い方法です。
参照:よくある質問(dodaチャレンジ)
dodaチャレンジの口コミは?その他の障がい者就職サービスと比較
障がい者雇用に特化した転職・就職支援サービスは年々増えてきていますが、「どのサービスが自分に合っているのか分からない」と悩む方も多いのではないでしょうか。
中でも、dodaチャレンジは知名度も高く、サポート体制や求人数においてバランスの良いサービスとされています。
とはいえ、他にも実績あるサービスは複数存在しており、それぞれ特徴や強みが異なります。
たとえば、就労移行支援に力を入れている「LITALICOワークス」や、IT・発達障害に特化した「Neuro Dive」、大手転職会社が運営する「アットジーピー」など、目的やサポートスタイルによって向き不向きがあるのも事実です。
ここでは、dodaチャレンジを含めた主要な障がい者就職サービスを「求人数」「対応地域」「対応障害」といった観点で比較した一覧表をご紹介します。
自分に合ったサービスを見極めるための参考にしてくださいね。
| 就職サービス名 | 求人数 | 対応地域 | 対応障害 |
| dodaチャレンジ | 1,500 | 全国 | 全ての障害 |
| アットジーピー(atGP) | 1,500 | 全国 | 全ての障害 |
| マイナビパートナーズ紹介 | 350 | 全国 | 全ての障害 |
| LITALICOワークス | 4,400 | 全国 | 全ての障害 |
| 就労移行支援・ミラトレ | 非公開 | 全国 | 全ての障害 |
| ランスタッドチャレンジ | 260 | 東京、神奈川、千葉、埼玉、大阪 | 全ての障害 |
| Neuro Dive | 非公開 | 全国 | 全ての障害 |
| Cocorport | 非公開 | 首都圏、関西、東海、福岡 | 全ての障害 |
dodaチャレンジ/専門エージェントが在籍、非公開求人も豊富
dodaチャレンジは、パーソルグループが運営する障がい者向けの転職支援サービスで、特に「専門性の高いエージェントが対応してくれる」という点で非常に評価が高いです。
障がい特性や配慮事項に理解のある担当者が在籍しており、安心して相談できる環境が整っています。
精神・発達・身体など、障がいの種類を問わず、一人ひとりに合った働き方を一緒に探してくれるのが魅力です。
求人数も非常に豊富で、公式サイトに掲載されていない「非公開求人」が多数あるのもdodaチャレンジの強みです。
これらは、大手企業や優良企業の採用枠で、一般には出回らないため、dodaチャレンジに登録することで初めてアクセスできる情報となります。
職種も事務職から専門職、在宅ワークまで幅広く、キャリアアップを目指す方にもおすすめです。
また、履歴書や職務経歴書の添削、模擬面接、企業との条件交渉など、応募から内定・入社後のフォローまで一貫したサポートが受けられるのも大きな安心材料。
転職が初めての方はもちろん、以前うまくいかなかった方にも、心強い伴走者になってくれるサービスです。
関連ページ:dodaチャレンジの口コミはどう?障害者雇用の特徴やメリット・デメリットをやさしく解説
LITALICOワークス/全国130拠点以上、再就職の安心感が魅力
LITALICOワークスは、就労移行支援サービスの中でも特に知名度が高く、全国に130以上の拠点を展開しているのが大きな特徴です。
「障害があることで働くことに不安がある」「以前の職場でうまくいかなかった」という方でも、安心して再スタートが切れるよう、個別サポートを徹底して行ってくれます。
LITALICOワークスの魅力は、何といってもその手厚いサポート体制。
個別面談はもちろん、ビジネスマナーの基礎から社会的スキルのトレーニング、模擬面接、職場実習まで、実践的なカリキュラムが整っているため、就職がゴールではなく「働き続ける」ことを重視している点が信頼されています。
また、全国各地に事業所があるので、地方在住の方でも通いやすい環境が整っており、地域密着型の就職支援が受けられるのも嬉しいポイントです。
支援員の方も福祉や就労支援の専門知識を持った方が多く、利用者一人ひとりの特性や状況に合わせて丁寧にサポートしてくれると評判です。
就職活動に自信がない方、久しぶりに働く方にも「ここなら大丈夫かも」と感じられる、安心感のあるサービスです。
関連ページ:LITALICOワークスの口コミ・評判は?就労移行支援の障害者支援内容と就職実績を徹底解説
ランスタッド/世界最大級の人材会社、障害者採用支援も対応
ランスタッドは、世界39カ国に拠点を持つグローバルな人材サービス会社で、信頼性と実績において非常に高い評価を受けています。
一般の転職支援だけでなく、障がい者雇用にも力を入れており、専門チームが障がいのある方の就職活動を丁寧にサポートしてくれるのが特徴です。
障害者採用支援では、専門のキャリアコンサルタントが常駐し、障がい内容や職場で必要な配慮事項を細かくヒアリング。
そのうえで、適切な求人を紹介してくれるため、ミスマッチの少ない就職を実現しやすいと評判です。
また、企業側とも密に連携しているため、就職後も安心して働ける体制が整っています。
特に東京・神奈川・千葉・埼玉・大阪といった都市圏に強く、通勤しやすい勤務地を希望している方には心強い味方になります。
業種も事務、軽作業、ITなど幅広く取り扱っており、正社員を目指す方にも十分な選択肢が用意されています。
大手外資系ならではのノウハウとネットワークを活かしたサポートが魅力で、転職活動に安心と信頼を求める方におすすめのサービスです。
関連ページ:「ランスタッド 口コミ」
ランスタッドのアフィリリンク
atGPジョブトレ/IT系や大手企業の障害者求人が豊富
atGPジョブトレは、障がいのある方を対象とした「就労移行支援サービス」で、特にIT系や大手企業とのつながりが強いのが特徴です。
ITスキルや事務スキル、コミュニケーション能力など、就職に必要なスキルを段階的に学べるカリキュラムが整っており、「就職がゴール」ではなく「長く働ける職場」を目指して支援してくれるのが魅力です。
企業連携に力を入れており、職場実習や職場見学の機会も豊富です。
実際に職場の雰囲気を体験したうえで、自分に合った企業を選べるため、就職後のミスマッチを防ぎやすくなっています。
また、就職先には大手企業や有名企業が多く含まれており、安心して働ける環境を求めている方にとっても心強い選択肢となります。
さらに、障がい特性に応じた専門コースがあるため、発達障害・うつ・統合失調症など、さまざまな特性に合わせた支援が受けられます。
個別支援計画のもと、無理のないペースで訓練が進められるので、体調や気分に波がある方でも安心して取り組むことができます。
実績豊富で、定着率も高いため、ITスキルを身につけたい方や、大手企業で安定して働きたいと考える方には非常におすすめのサービスです。
関連ページ:atGPジョブトレ 口コミ・評判は本当?|利用者のリアルな声と就職体験談
ミラトレ/就職後も手厚くサポート、パーソルグループ運営
ミラトレは、就職支援に強みを持つ「パーソルグループ」が運営する就労移行支援サービスです。
就職までの支援はもちろんですが、特に「就職してからが本番」と考えているのがミラトレの大きな特徴で、職場定着までをしっかりサポートしてくれます。
利用者の声としても、「就職したあとも気にかけてくれた」「不安な時にすぐ相談できた」という感想が多く、長く働き続けるための心強い味方になってくれると評判です。
支援内容としては、ビジネスマナーやコミュニケーションのトレーニング、応募書類の作成サポート、模擬面接など、実践的なカリキュラムが充実しています。
さらに、ミラトレは全国の主要都市に複数の拠点があるため、通いやすさも魅力の一つです。
精神・発達・知的など、さまざまな障がいに対応しており、個別性を重視した支援計画を立ててくれます。
また、パーソルグループならではのネットワークを活かした求人提案もあり、企業とのマッチング精度が高い点もポイント。
利用者の「働く自信」を引き出し、「安心して働き続けられる環境」を整えることに本気で取り組んでいるサービスです。
関連ページ:ミラトレの口コミ・評判を検証|実際に通った人の声から見えた支援の中身
dodaチャレンジの口コミは?障害者雇用の特徴・メリット・デメリットまとめ
障害のある方が就職・転職を考える際、最も不安を感じやすいのが「自分に合った仕事があるのか」「配慮してもらえる環境で働けるのか」という点です。
そんな悩みに寄り添ってくれるのが、dodaチャレンジのような障害者雇用専門の転職支援サービスです。
dodaチャレンジは、障害特性に配慮した求人の紹介はもちろん、キャリアアドバイザーが履歴書添削から面接練習、企業との条件調整までをサポートしてくれるのが特徴です。
求職者と企業の双方にとって“無理のないマッチング”を重視しており、働き始めてからの定着支援にも力を入れています。
この記事では、dodaチャレンジを実際に利用した人たちの口コミをもとに、障害者雇用のリアルな特徴や、メリット・デメリットを整理して紹介していきます。
「障害者雇用ってどんな感じ?」「普通の転職とどう違うの?」という疑問をお持ちの方にもわかりやすくまとめているので、ぜひ参考にしてみてくださいね。